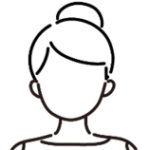 保護者
保護者不登校の子どもって、心療内科に連れて行ったほうがいいんでしょうか・・・
不登校が改善しない、子どもと心が離れていくような感じがする。
カウンセリングに行っても改善の兆候が見られない。
そんなとき「心療内科」という言葉が頭をよぎると思います。
この記事では具体的な子どものサインから「心療内科を受診する判断基準」を紹介しています。しかし、心療内科という「医者」に行くのは抵抗があるもの。そんなとき親はどのように行動したらいいのか。そのことについても提案してます。



私自身も心療内科に1年以上通院してお世話になりました。心療内科については詳しい方だと思います。
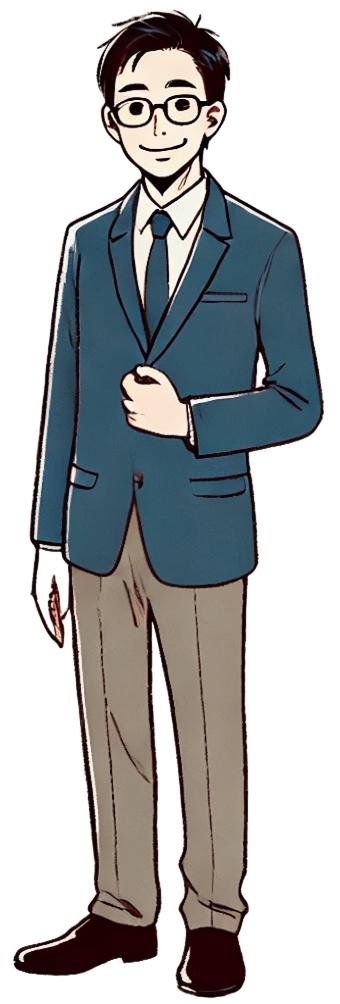
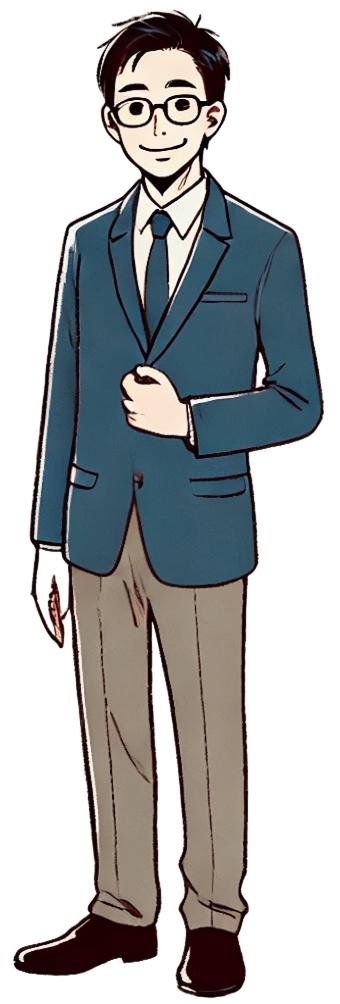
- もと中学校の教員 35年間勤務
- アドラー心理学、認知行動療法、コーチングなどを学ぶ
- 「子どもに一生懸命でない保護者はいない」が信条
- 現在も教育関係の仕事に従事
- 自分の子どもが2人とも不登校を経験。
- その経験から不登校についての発信を始める。
ここのサイト管理者「Kon」は医師ではありません。あくまでも自分自身の経験談ともと教師としての目線からの記事としてお読みください。
こんなサインがあれば心療内科を検討すべき 受診の判断基準3つ


「うちの子、このまま様子を見ていて大丈夫?」
「病院に行くほどではない気がするけど、どう判断すればいいの?」
不登校になった子どもを前に、多くの親が悩むのが 「心療内科を受診するべきタイミング」 です。
ここでは 心療内科の受診を考えた方がよい3つの判断基準 を紹介します。



もし 1つでも当てはまる場合 は、専門家に相談することをおすすめします。
- 基準① 身体的なサイン:朝起きられない、頭痛や腹痛が続く、食欲不振
- 基準② 精神的なサイン:理由のない不安、強いイライラ、自己否定が増える
- 基準③ 行動のサイン:極端に外出を嫌がる、家族と会話しなくなる、昼夜逆転
基準① 身体的なサイン:朝起きられない、頭痛や腹痛が続く、食欲不振
身体的な症状が長引いているなら、心療内科の受診を考えるべきです。
心と体はつながっています。精神的なストレスがたまると、 「体の不調」 という形で現れることがあります。



特に、不登校の子どもは 「学校に行かなきゃ…でも行けない」 という葛藤の中で、無意識に体調を崩すことが多いのです。
具体的な症状
- 朝になると頭痛や腹痛がひどくなる(登校時間が過ぎると症状が和らぐ場合も)
- 食欲が極端に落ちたり、逆に過食気味になったりする
- 夜眠れず、昼夜逆転の生活になってしまう
✅ 対処のポイント
病院に行く前に、 「風邪などの身体的な病気ではないか?」 を確認するのも大切です。
内科で問題がないと言われた場合は、 心の不調が原因の可能性が高い ので、心療内科の受診を考えてみてください。
基準② 精神的なサイン:理由のない不安、強いイライラ、自己否定が増える
不安や自己否定が強くなっている場合、心療内科での相談が必要な可能性が高いです
不登校が続くと、 「自分はダメな人間だ」 と思い込んでしまう子どもがいます。



周りと比べてしまったり、このままじゃ将来どうなるの?、と考えてしまい、 不安が強くなり、精神的に追い詰められることがあるんです。
具体的な症状
- 「どうせ自分なんて…」と自虐的な発言が増える
- 些細なことで怒りやすくなる(親や兄弟に対して強く当たる)
- ひどく落ち込む日と元気な日が極端に分かれる
✅ 対処のポイント
こうしたサインが見られる場合は、まず 「大丈夫?何か話したいことある?」 と声をかけてみてください。
ただし、 しつこく聞くと逆効果になることもある ので、子どもが話しやすいタイミングを待つことが大切です。
それでも状況が改善しない場合は、専門家に相談するか心療内科を受診するか考えましょう。
基準③ 行動のサイン:極端に外出を嫌がる、家族と会話しなくなる、昼夜逆転
家族との会話や外出を極端に避けるようになったら、心療内科の受診を検討すべきです。
不登校の子どもは、 「自分を責める気持ち」 から誰とも関わりたくなくなることがあります。



昼夜逆転の生活 になってしまうと、社会との接点がますます少なくなり孤立しがちになってしまいます。
具体的な症状
- 「外に出たくない」と家から一歩も出なくなる
- 親が話しかけても「別に」「わからない」としか答えなくなる
- 昼間に寝て、夜中にスマホやゲームをする生活が続く
✅ 対処のポイント
まずは無理に外出を促さず、「一緒に○○しよう」と軽く誘うことが大切 です。
たとえば、 「ちょっとコンビニ行かない?」「家の前を散歩しよう」 くらいの軽い誘いなら、子どもも応じやすいです。
それでも 外に出るのを拒否し、家族ともほとんど話さなくなったら、専門家の力を借りることを考えたください。
「心療内科に行こう」と言ったら嫌がられる?子どもが納得しやすい伝え方5つ


「心療内科に行ってみない?」と伝えた途端、子どもが 「絶対に行きたくない!」 と拒否する…。
そんな場面に直面し、どう説得すればいいか悩む親は少なくありません。
子どもにとって 「心療内科=病気の人が行く場所」 というイメージが強く、 「自分は異常なの?」と誤解してしまう ことが多いためです。
しかし、伝え方を工夫することで、子どもが受診に前向きになる こともあります。
ここでは、 子どもが心療内科を受診しやすくなる5つの伝え方 を紹介します。
- 伝え方① 「カウンセリング感覚でOK」と伝える
- 伝え方② 「診断よりも話を聞いてもらう場」と説明する
- 伝え方③ 「私(親)が先に行ってみるね」と提案する
- 伝え方④ 信頼できる第三者に勧めてもらう
- 伝え方⑤ いきなり病院ではなく、学校のカウンセラーなどから始める
伝え方① 「カウンセリング感覚でOK」と伝える
「病院に行く」というより、「話を聞いてもらいに行く」感覚を持たせるのが効果的です。
心療内科と聞くと、子どもは 「薬を飲まされるの?」「入院させられるの?」 と不安を感じやすいです。



心療内科でも 「いきなり薬を処方する」ことはなく、まずは話を聞くことが基本」 なのです。
ポイント
- 最近の心療内科は 「相談する場所」 としての役割が大きい
- 受診=治療ではなく、「どうすれば楽になるか」を一緒に考える場
- 医師も、すぐに診断や薬の処方をするわけではなく、様子を見ながら進める
✅ 具体的な伝え方
「病院っていうより、相談できる場所なんだって」
「悩んでる人が行くカウンセリングみたいなものだよ」
伝え方② 「診断よりも話を聞いてもらう場」と説明する
「診断を受けるために行くのではなく、気持ちを整理するために行く」と伝えると納得しやすい。
子どもは 「病院=病気」 と思い込んでいることが多いものです。



「自分が精神的な病気だと決めつけられるのでは?」 という不安を持っているわけです。
ポイント
- 近年の心療内科では「治療」よりも「メンタルサポート」の役割が強まっている
- 実際に診断名がつかなくても、相談だけで受診できるクリニックも多い
- カウンセリングだけを受ける選択肢もある
✅ 具体的な伝え方
「お医者さんに話を聞いてもらうだけでもいいらしいよ」
「今の気持ちを整理するために、一回相談してみるのはどうかな?」



私も行くときには「病気」という言葉が頭をよぎりました。
けれどカウンセリングを受けても改善する気配がなかったため「一回くらい相談してみるか」という感覚で受診しました。
伝え方③ 「私(親)が先に行ってみるね」と提案する
子どもが嫌がるなら、まず親が受診し、その経験を伝えるのも有効な方法です。
子どもは 「知らない場所に行くこと」 に強い不安を感じます。



親が先に行くことで、「こんな感じだったよ」と具体的に説明できる」 ので、子どもが安心しやすくなります。
ポイント
- 親が受診してみると、「心療内科の雰囲気」「先生の人柄」などを事前に伝えられる
- 子どもが「じゃあ、少しなら話を聞いてみてもいいかな」と思うきっかけになる
- 親自身のストレスケアにもなり、一石二鳥
✅ 具体的な伝え方
「お母さん(お父さん)も行ってみようかなと思うんだけど、一緒にどう?」
「まず私が行ってみるから、その後考えてみてもいいよ」
伝え方④ 信頼できる第三者に勧めてもらう
親が言うと反発する子どもでも、信頼できる先生や友人、親族に勧められると納得しやすいことがあります。
思春期の子どもは 「親に言われると素直に聞けない」 ことがよくあります。



学校の先生やカウンセラー、信頼できる先輩や親族に言われると、納得することが多いんですよね。
ポイント
- 「親には相談しにくいけど、先生には話せる」という子どもも多い
- 第三者からの提案なら「押し付けられている」と感じにくい
- 実際に、先生やスクールカウンセラーがきっかけで受診につながるケースも多い
✅ 具体的な伝え方
「(心療内科の)受診について、誰か相談したい人はいない?」
「(心療内科の)受診についてカンセリングの先生に相談してみようか」



私も当時の上司から強く勧められました。上司から言われたのはショックでしたが、今では感謝しています。
伝え方⑤ いきなり病院ではなく、学校のカウンセラーなどから始める
心療内科へのハードルが高いなら、まずは学校のカウンセラーやオンライン相談から始めるのも一つの方法です。
いきなり病院に行くのはハードルが高いため、 「相談の第一歩」 としてカウンセラーやオンラインのメンタルサポートを活用するのが効果的です。



「振り出しに戻る」のような考え方ですが、カウンセリングを利用していない子どもさんなら、まずはここからでしょう。
ポイント
- 学校のスクールカウンセラーなら、通学しなくても相談できる場合がある
- 匿名のオンライン相談なら、気軽に話せる子どもも多い
- 「まず話をしてみる」ことが、心療内科受診のステップにつながる
✅ 具体的な伝え方
「いきなり病院じゃなくて、カウンセラーさんと話してみるのはどう?」
「家からでも相談できるサービスがあるみたいだよ」
子どもが安心できるクリニックの選び方と受診の具体的な方法
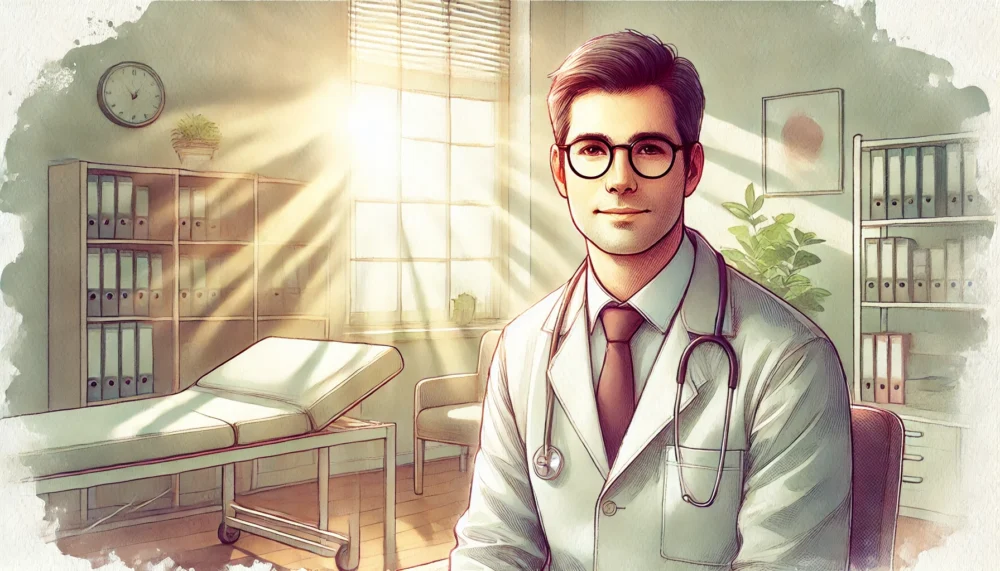
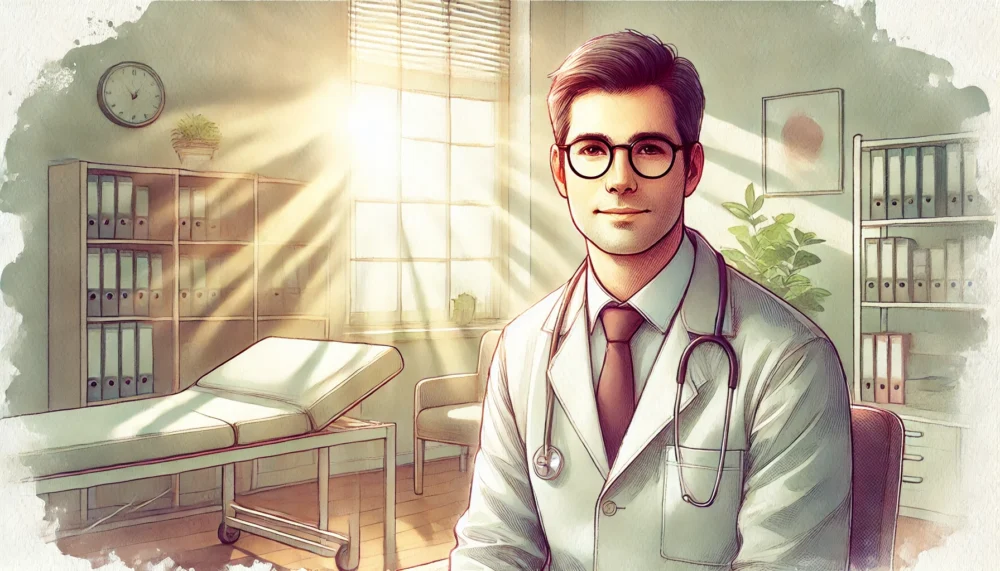
「心療内科に行くことを決めたけど、どのクリニックを選べばいいの?」
「初めての受診って、どんな流れになるの?」
いざ心療内科に行くと決めても、どのクリニックを選ぶべきか、どう受診すればいいのか分からない という親は多いです。
実は、心療内科は 「どこでも同じ」ではなく、子どもに合った場所を選ぶことがとても重要 です。
ここでは、子どもが安心して受診できるクリニックの選び方と、スムーズな受診方法 について3段階に分けて解説します。
- 子どもに合った心療内科とは
- 受診前に準備してくことは
- 最初の診察の流れ
子どもに合った心療内科とは
「子ども専門の診療があるか」「医師やスタッフの雰囲気」「通いやすさ」をチェックしましょう。
心療内科はクリニックによって雰囲気や診療方針が異なります。
特に 思春期の子どもはデリケートなため、「子ども向けの診療に慣れているか」 が大切なポイントになります。
クリニック選びのチェックポイント
- 思春期専門の医師がいるか? → 小児精神科や思春期専門の診療があるかを確認
- 口コミや評判はどうか? → Googleマップや病院検索サイトのレビューをチェック
- 予約の取りやすさは? → 初診まで数カ月待ちのところもあるため、早めに確認
- 親子で一緒に受診できるか? → 初回は親子で話を聞いてもらえるクリニックが安心
✅ 具体的な探し方
- 「○○市 心療内科 思春期」 で検索
- 学校や市の相談窓口に問い合わせ(スクールカウンセラーや教育委員会の窓口)
- ママ友や知人に口コミを聞く(意外と良い情報が手に入る)



私は地元に1軒しかない心療内科にお世話になりました。
最初は不安でしたが、親身に相談に乗っていただき、とても助かりました。
地方で長年経営しているクリニックはそれだけで、ある程度の信頼があることになります。
地元のクリニックには行きたくない、という事情があれば別ですが、遠隔地の有名なところを探す前に、まず行ってみることをおすすめします。
受診前に準備しておくことは
初診の際は「子どもの現状が分かるメモ」を持参し、予約や問診票の準備をしておくとスムーズに進みます。
初診では、医師が子どもの状態を把握するために詳しく話を聞く ことが多いです。
しかし、親も子どもも緊張して 「何を話せばいいか分からなくなる」 ことがあるため、事前準備が大切なのです。
つぎのことを受診前に準備しておくと良いでしょう。
- 子どもの状態メモを作成する
- いつ頃から不登校になったか
- 学校を休むようになったきっかけ
- 生活習慣の変化(寝る時間、食欲の有無)
- 親や先生との会話の様子
- 問診票の記入(可能なら事前にダウンロード)
- クリニックのHPから問診票をダウンロードできる場合もあるので、記入しておくと時短に
- 子どもが話しやすいようにリラックスさせる
- 「難しいことを聞かれるかも」と不安になる子どもも多いため、「何を話してもOKだよ」と安心させる



子どもにも安心できる声がけが必要ですね。
✅ 子どもには「何を言ってもいいよ。」「言っていけないことはないよ。」「自分(保護者)がいないほうがいいとは伝えてね。」などと事前に伝えておくことをおすすめします。
最初の診察の流れ
初診では「問診・カウンセリング・診察」がメインで、いきなり薬を処方されることはほとんどありません。
心療内科では、まず 「どんな悩みがあるのか?」を丁寧に聞き取る ことが最優先です。
そのため、初診からすぐに治療が始まるわけではなく、まずは「話を聞くこと」からスタート します。
初診の流れ
- 受付・問診票の記入(事前に書いていればスムーズ)
- 親子でのカウンセリング(親と子ども、それぞれの話を聞く)
- 診察(必要なら簡単なテストや心理チェックをする場合も)
- 今後の方針を決める(薬を出すか、カウンセリングを続けるかなど)



初診後には次のことに気をつけましょう。
- 子どもが「行ってよかった」と思えるような声かけをする
→ 例:「先生、話をよく聞いてくれたね」「思ったより怖くなかったね」 - 次回の予約を取るかどうか、子どもと相談する
→ 無理に通わせるのではなく、子どもの気持ちを尊重することが大切
まずは親が受診するのも一つの手!その理由3つ


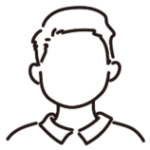
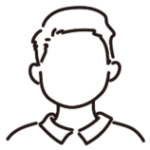
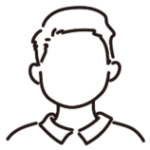
「子どもが心療内科を嫌がるけど、このまま何もしなくていいのかな?」
「親ができることはないだろうか?」
不登校の子どもを持つ親は、日々 「どうすればいいのか?」 という悩みと向き合っています。
しかし、子どもが受診を拒否していると、何もできないように感じてしまうこともあるでしょう。
そんなときに有効なのが、「まず親が心療内科を受診すること」 です。
「え、親が?」と思うかもしれませんが、これは 子どものためにも、親自身のためにも大きなメリット があります。
ここでは、親が受診することが有効な 3つの理由 を紹介します。
- 理由① 親自身のメンタルケアも大切!「子どもを支えるには、親が元気でいることが重要」だから
- 理由② 子どもに「病院は怖くない」と伝えられる!「こんな感じだったよ」と体験を共有できるから
- 理由③ 医師から子どもへのアプローチを学べる!「どう接するのがベターか」などのアドバイスがもらえるから
理由① 親自身のメンタルケアも大切!「子どもを支えるには、親が元気でいることが重要」だから
子どもを支えるには、まず親自身が心の余裕を持つことが大切です。
不登校の子どもを持つ親は、知らず知らずのうちに 大きなストレスやプレッシャーを抱えている ことが多いです。
「子どものために頑張らなきゃ!」と思うのは素晴らしいことですが、親のメンタルが不安定だと、結果的に子どもにも悪影響を与えてしまいます。



親が焦ると、無意識に子どもにプレッシャーを与えてしまうことがありますし、「自分のせいで親が疲れてる…」と子どもが罪悪感を抱くこともあります。
まずは、親自身が無理をしていないかを振り返ってみましょう。
理由② 子どもに「病院は怖くない」と伝えられる!「こんな感じだったよ」と体験を共有できるから
親が先に受診してみることで、子どもに「心療内科の雰囲気」を伝えやすくなります。
心療内科に対して、子どもは 「何をされるのかわからない」「行ったら病気扱いされるんじゃ…?」 という漠然とした不安を持っています。



親が先に受診すれば、 「実際に行ってみたけど、こんな感じだったよ」 と伝えることができ、子どもの不安を軽減できます。
✅ 家族だけではなく、知人や信頼の置ける方が受診の経験があるのであれば、その方から体験談を語ってもらうのもとても有効です。
理由③ 医師から子どもへのアプローチを学べる!「どう接するのがベターか」などのアドバイスがもらえるから
親が受診することで、専門家から「不登校の子どもへの接し方」のアドバイスを受けられます。
子どもが不登校になると、「どう声をかければいいのか?」「このまま見守るのがいいのか?」と悩むことが多くなります。
親自身が心療内科で相談することで、 「子どもにどう接するのがいいのか?」 という具体的なアドバイスをもらうことができます。



実際は医師から子どもの様子を問診されることが一般的です。医師は子どもに関する情報がないので。
それを聞き出してくれる中で、親の悩みを打ち明けたり、アドバイスを貰うことができるのです。
医師からアドバイスを貰って子どもの状況が好転することは実はよくあることです。
それは「親の子どもへの接し方が変わる」からです。その点に特化したサービスもあります。
スダチです。多くの実績を上げていますので、興味のある方は一度ご覧になってください。
「行動」こそが大切


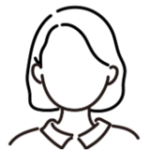
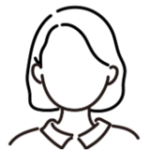
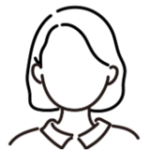
「心療内科を受診するのって、本当に意味があるの?」
「病院に行ったからといって、不登校がすぐに解決するわけじゃないのでは…?」
心療内科の受診を考えている親の中には、「受診が本当に正しい選択なのか?」 と迷う人も多いでしょう。
しかし「心療内科の受診を考え、実際に行ってみる。」という「行動」そのものが良い変化をもたらす原動力なのです。
まずは「受診すること」が大事!1回行ってみてから考えよう
心療内科を継続するかどうかは、一度受診してから決めればOK。まずは一歩踏み出すことが大切です。
「病院に行ったら、ずっと通い続けなきゃいけないの?」と心配する親も多いですが、そうではありません。
受診するだけでも、「どうすればいいか」が見えてくることが多い ため、迷っているなら まずは1回行ってみることが重要 です。



なんでもそうですが、「試してみないとわかりません。」
たしかに「行かないほうがマシだった」ということも考えられます。
しかし、ある程度長期で開業しており、地域に根ざしているようなところであれば、最悪でも「時間の無駄」くらいで済みます。
受診の心がまえ
受診する側、つまり子どもと保護者ですが、特に保護者の方には、ある「心がまえ」を持っていただきたいと思います。
それはカウンセリングや、心療内科は患者側が過剰な期待を持つと、失望することが多い。
ということです。



「権威のある外部機関」にかかる場合、どうしても期待してしまいます。
依存したくなる、と言い換えてもいいです。
「誰かがなんとかしてくれ」と思いたくなるのです。
しかし、不登校の改善には、親が覚悟を持つことが必要です。
そして時間が必要です。「じっくり効く漢方薬的な方法」でなければ改善できないのです。
よくある質問とその回答
- Q1. 子どもが「心療内科には絶対行きたくない!」と言っています。どうすればいいですか?
-
子どもが受診を拒否するのは、ごく自然な反応です。無理に説得しようとすると逆効果になりやすいため、まずは「話を聞いてもらうだけでもいいんだよ」と軽く伝えてみましょう。また、親自身が先に受診し、「お母さん(お父さん)も相談してきたんだけどね」と体験談を話すのも有効です。子どもが安心できるような伝え方を工夫し、焦らず寄り添う姿勢が大切です。
- Q2. 受診したらすぐに薬を処方されるのでしょうか?
-
多くの心療内科では、初診でいきなり薬を出すことはほとんどありません。まずはカウンセリングを通じて、現在の状況を把握することから始まります。必要があれば医師が薬を勧めることもありますが、親子で相談した上で決められます。不安な場合は、「できるだけ薬を使わずに様子を見たい」と事前に伝えておくと安心です。
- Q3. 受診をすると、学校に通えるようになりますか?
-
心療内科の受診は、不登校の根本的な原因を探る手助けになりますが、すぐに学校に戻れるわけではありません。医師との対話を通じて、子ども自身が「どうすれば楽になれるか?」を知ることが重要です。学校復帰を焦るよりも、まずは子どもが安心できる環境を整えることを優先しましょう。小さなステップを積み重ねることが、最終的な解決につながります。
- Q4. 心療内科とカウンセリングの違いは何ですか?
-
心療内科は医師が診察し、必要に応じて薬を処方したり、医学的なアドバイスを行う場です。一方、カウンセリングは心理士などの専門家が話を聞き、気持ちの整理をサポートすることが目的です。どちらを利用するか迷った場合、まずはカウンセリングで相談し、必要があれば心療内科を受診するのも一つの方法です。
- Q5. 子どもが受診を嫌がる場合、親だけで行っても意味がありますか?
-
親だけの受診も十分に意味があります。心療内科では、不登校の子どもに対する適切な接し方について専門的なアドバイスを受けることができます。また、親自身のストレスを軽減するためのサポートも期待できます。子どもが受診を拒否している間も、親ができることはたくさんありますので、まずは親自身が相談に行くのも良い選択です。
- Q6. どのような心療内科を選べばいいのでしょうか?
-
心療内科にはさまざまなタイプがあり、特に思春期の子どもを専門とするクリニックが適しています。子どもがリラックスできる雰囲気か、診察の待ち時間が短いか、親子で話を聞いてもらえるかといった点を確認しましょう。また、事前に口コミを調べたり、学校のカウンセラーに相談して紹介してもらうのも有効な方法です。
- Q7. 受診後、子どもにどんな声かけをすればいいですか?
-
受診後は、「どうだった?」と無理に聞き出すのではなく、「今日はよく頑張ったね」「話を聞いてもらえてよかったね」とさりげなく声をかけるのがベストです。子ども自身も緊張しているため、まずは「受診したこと自体が大きな一歩だった」と認めてあげましょう。会話の中で、次の受診についても自然に触れられると安心感が生まれます。
- Q8. 心療内科に行くと学校や周囲に知られてしまうのでは?
-
通常、心療内科の受診が学校や第三者に伝わることはありません。個人情報の保護が徹底されているため、親が許可しない限り、医師が学校に連絡することもありません。ただし、学校と連携を取りたい場合は、親の判断で先生に相談することもできます。無理に伝える必要はなく、子どもが安心できる形を選びましょう。
- Q9. どのくらいの頻度で通うことになるのでしょうか?
-
受診の頻度は子どもの状態によって異なりますが、最初は2~4週間に1回のペースが一般的です。症状が安定してくると、通院の間隔を空けることもできます。また、医師と相談しながら、自宅でできる対策を増やしていくことで、徐々に受診回数を減らしていくことも可能です。無理のないペースで進めることが大切です。
- Q10. もし心療内科に行っても改善しなかったらどうすればいいですか?
-
心療内科の治療は時間がかかることもあります。一度の受診で劇的な変化が見られなくても、焦らずに様子を見ることが大切です。もし相性が合わないと感じた場合は、他の医療機関を検討するのも一つの方法です。また、カウンセリングやフリースクールなど、他の支援策も併用することで、子どもに合った解決策を見つけることができます。
まとめ
- 不登校の子どもがいる場合、心療内科の受診を検討する判断基準として、身体的な不調、精神的な変化、生活リズムの乱れなどのサインを見逃さないことが重要である。
- 子どもが受診を嫌がる場合は、「カウンセリング感覚で話を聞いてもらうだけ」と伝えたり、親が先に受診して体験を共有することで、不安を和らげる工夫が有効である。
- 心療内科を選ぶ際は、思春期の子どもに対応できる専門医がいるか、診療方針や雰囲気が合っているかを確認し、口コミや相談機関の情報も活用することが望ましい。
- 親自身が先に受診することで、ストレスを軽減し、適切な子どもへの接し方を学べるため、子どもが受診を拒否している間も積極的に行動することが大切である。
- 心療内科の受診は、不登校の根本的な解決につながる第一歩であり、まずは一度受診してみて、必要に応じて継続や他の支援策と組み合わせる柔軟な対応が求められる。
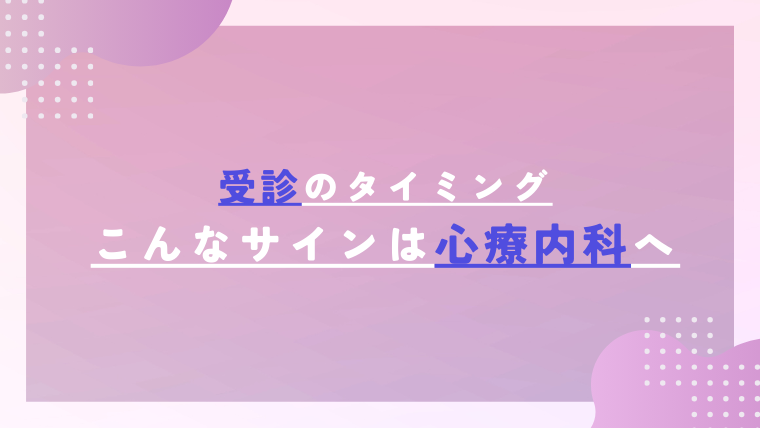
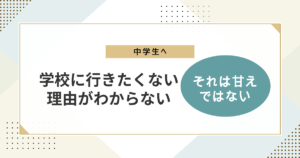
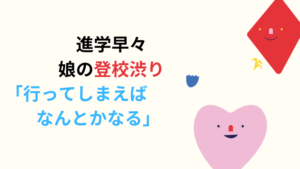
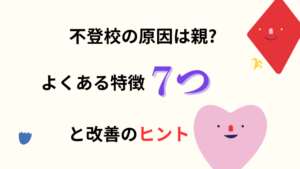

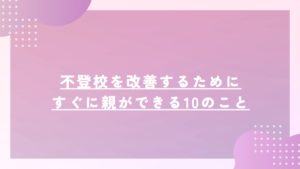

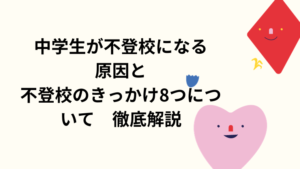
コメント