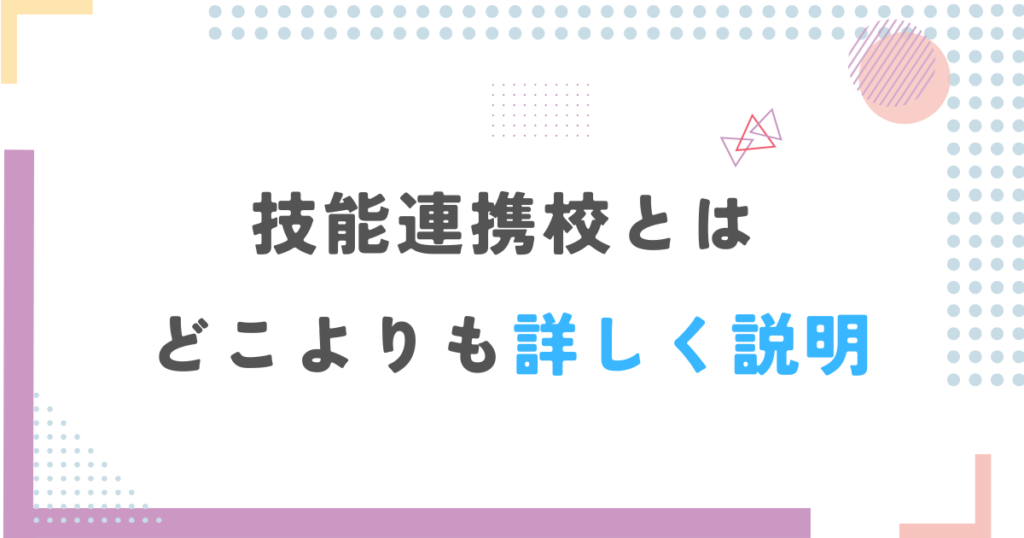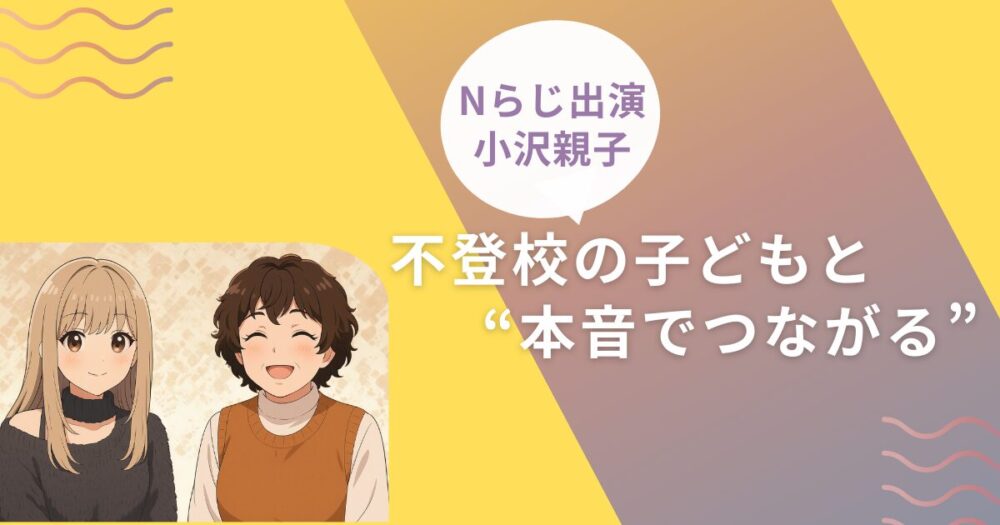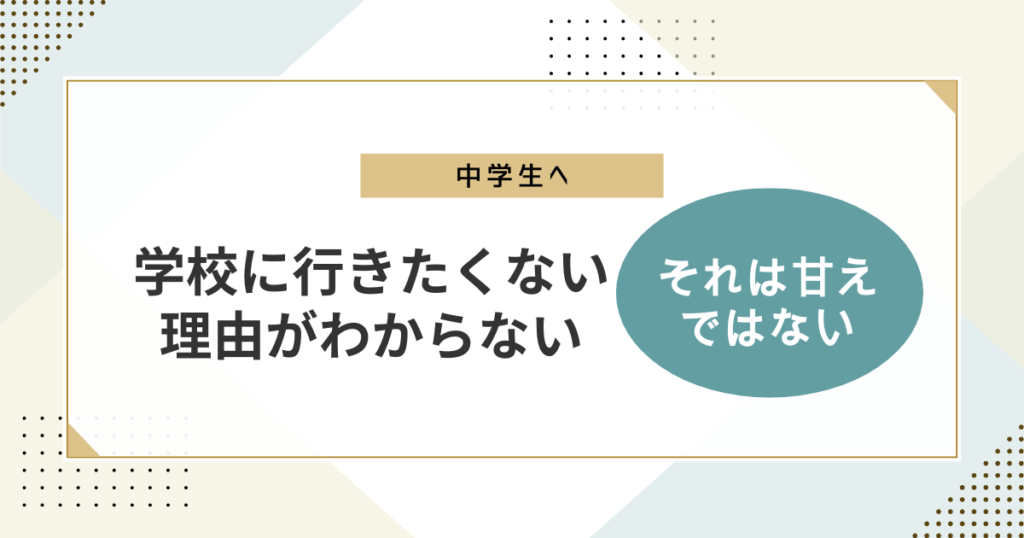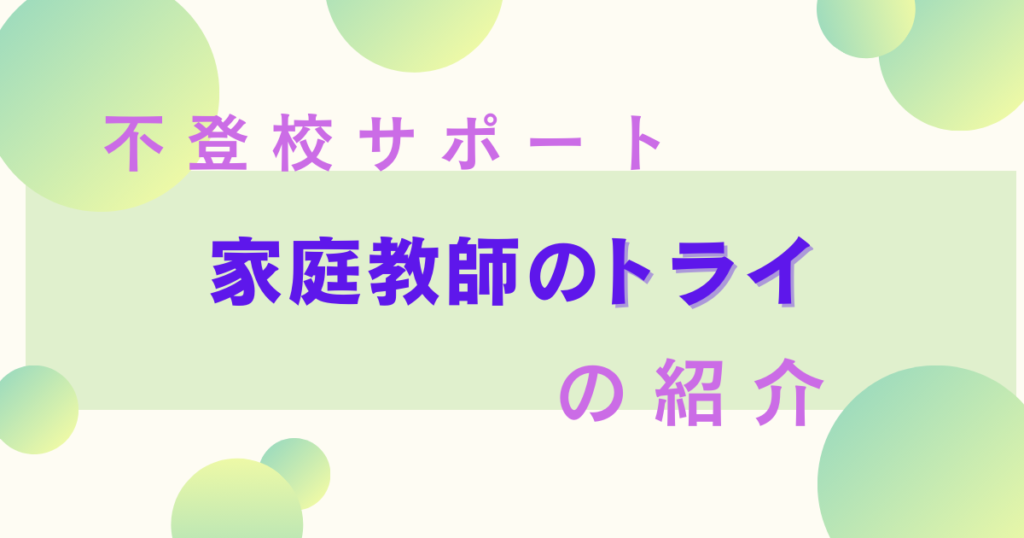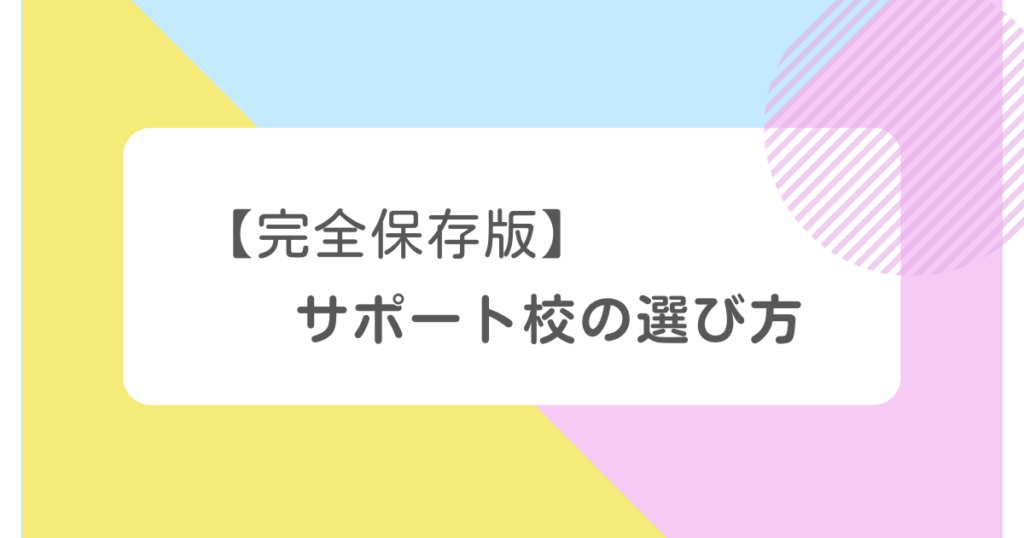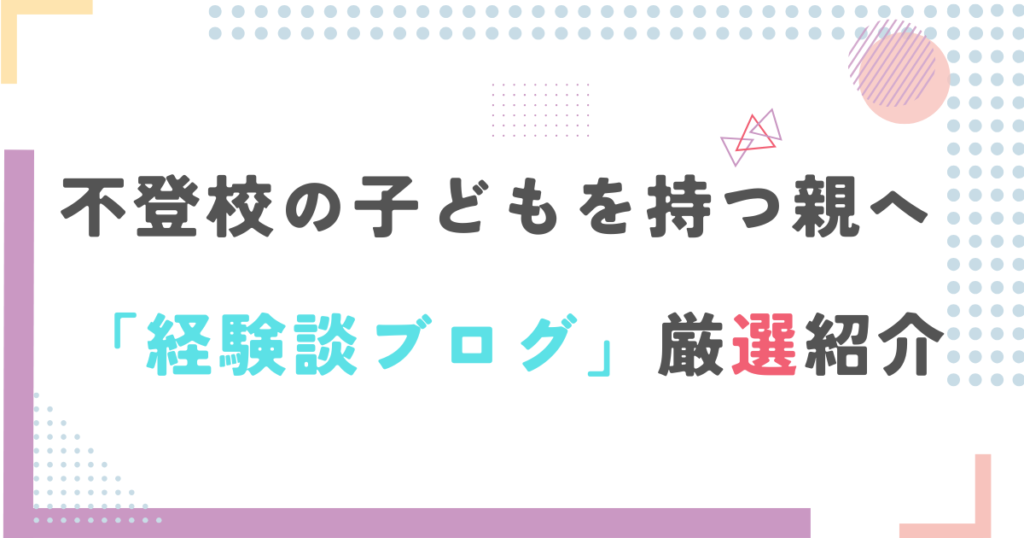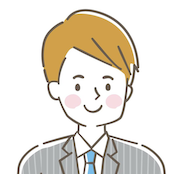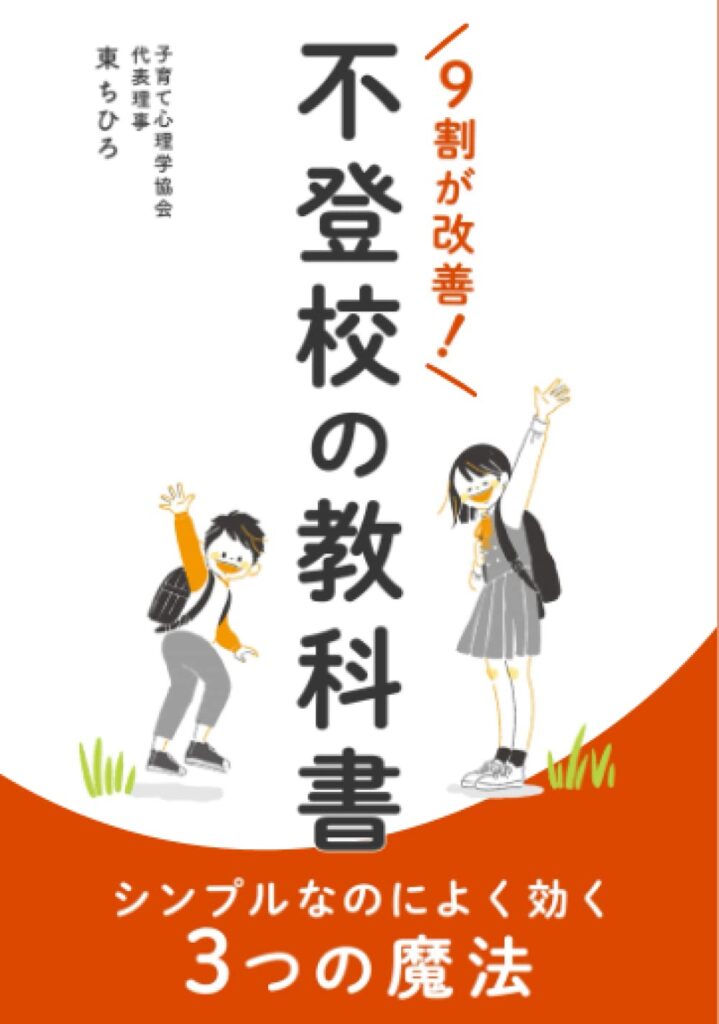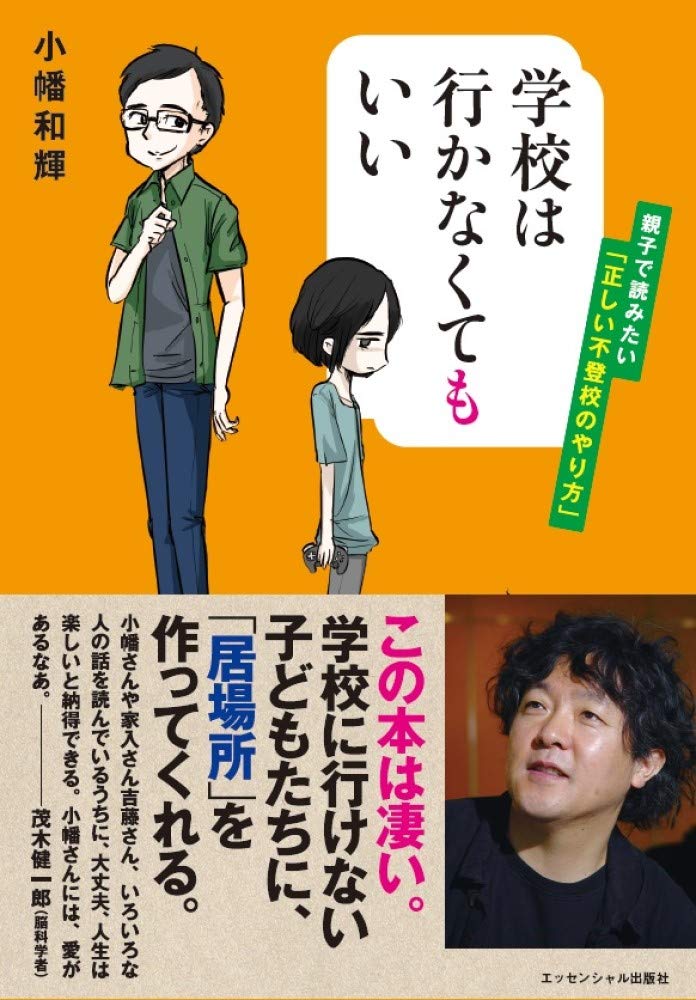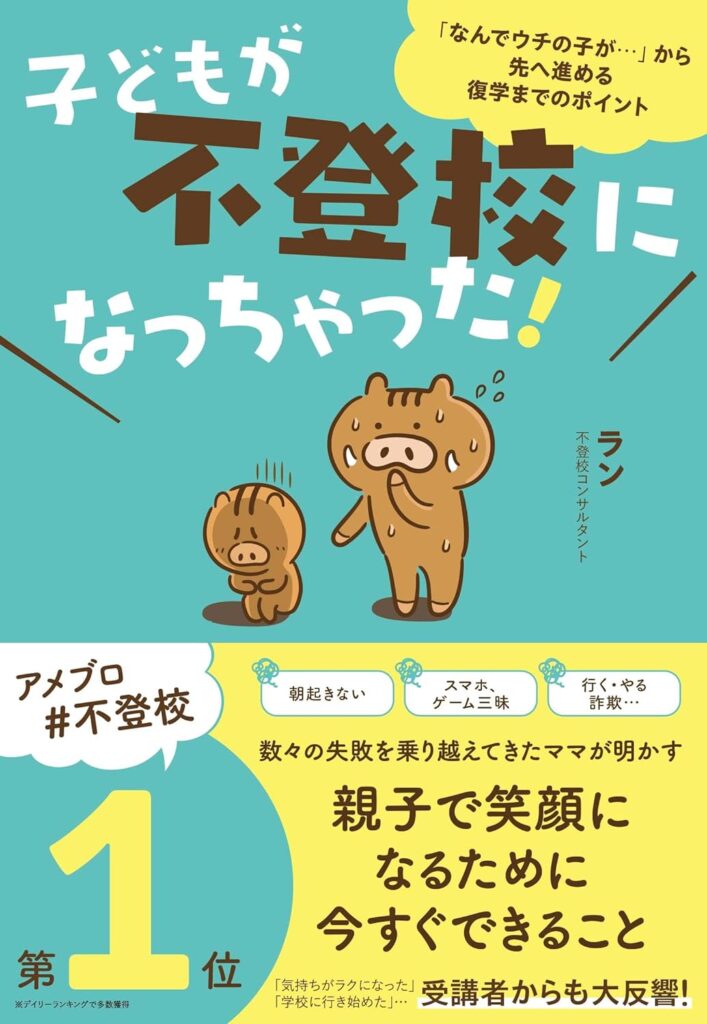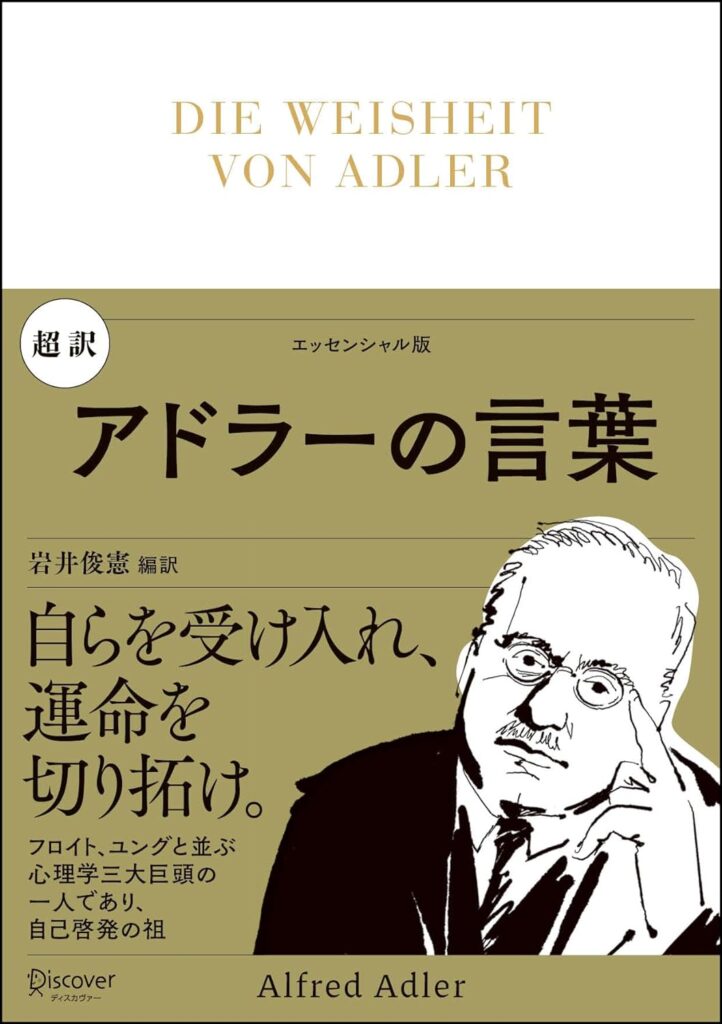不登校のお子さんを持つ親御さんへ
このサイトは、不登校のお子さん、特に中学で不登校になったお子さんを抱えているご家庭に寄り添った内容を発信できるよう心がけています。
インターネット上には、不登校に関する様々な情報が溢れ、何が本当に正しいのか分からなくなることもあるでしょう。
また、一見役立ちそうな情報でも、実は特定のサービスや商品に誘導するための記事が多いのも事実です。
この記事を書いているサイト管理者は、中学校教員として30年以上の経験を持ち、不登校の生徒たちとも数多く向き合ってきました。
学校に戻ることができた生徒も、そうでなかった生徒も、様々なケースを目の当たりにしてきました。
その豊富な経験をもとに、良質な情報を厳選してお届けします。
ただし、情報を手に入れるだけでは解決に結びつくことはありません。
大切なのは、その情報を基に行動を起こすことです。
このサイトでは、具体的にどのように行動すればよいのか、実践的なアドバイスも含めてご紹介いたします。
お子さんの未来を支えるために、一緒に学び、一緒に一歩を踏み出しましょう。
不登校のお子さんが心配でたまらない親に
この記事を読んでくださっている親の方々は次のように悩んでいらっしゃる方が多いと思います。
- 不登校になってしまったのは親の責任かもしれない、自分の何が悪いのだろう。
- 不登校には原因がある。学校で何かあったに違いない。
- 不登校を解決してもう一度元気に登校してもらいたい。
- このままずっと不登校だったらどうしよう。
- 不登校のことはどこに相談したらいいんだろう。
このサイトではこれらのことについて、少しでも役に立つような記事を多角的に書いています。

もと教員で多くの不登校の生徒に接してきた経験をもとに、皆さんに有用な情報を発信できるよう心がけています。
不登校 まず親に「心のエネルギー」を
「不登校の状態になっている」子どもや家庭に共通していることがあります。
それは「心のエネルギー不足」です。
心のエネルギーを別の言葉で表現すると「元気、やる気、根気」です。
このサイトで紹介している記事は、基本的に子どもに「心のエネルギー」を補給する方法です。
簡単に言えば「読んでいて希望が持てる」ものです。
しかし、実は不登校のお子さんを抱えている親も「心のエネルギー」が不足しています。
不登校が長期間にわたっていればそのエネルギーは枯渇してしまっているかもしれません。
「不登校疲れ」と言われる状態ですね。
不登校を解決するためには親自身に「心のエネルギー」の補給が必要です。
悩んでいるだけでは解決しません。
情報を仕入れるだけでも解決しません。
解決するには自分が正しいと思った情報をもとに行動を起こさなければなりません。
行動するには「心のエネルギー」が必要です。

このサイトを訪れるすべての皆さんに「心のエネルギー」が満たされることを願っています。
不登校の親と子のための水先案内
具体的に親は何をすればいいのでしょう。
最初にこのサイト内で読んでいただきたい記事を3つ紹介します。
https://manabou-issyo.com/geninn-kikkake/ https://manabou-issyo.com/futoukou-kaizen10/ https://manabou-issyo.com/jozuna-saborikata/これらを読んでいただければ、不登校を解決するための希望やヒントが持てるようになると思います。
本の紹介
不登校の解決のためには親自身が学び、行動する必要があります。
学ぶうえでの基本は「書籍」です。
ここではまず3冊の本を紹介します。
「不登校の教科書: 9割が改善! シンプルなのによく効く3つの魔法」東ちひろ 著
著者の 東ちひろ さんは子育て心理学協会という一般社団法人を主宰し、中学校でスクールカウンセラーもつとめています。
幼稚園講師、小学校教諭、中学校相談員、教育委員会を経て子育てカウンセリングの世界に足を踏み入れて30年、2万件以上のケースに対応してきた方です。
この本では
・「引きずってでも学校に連れて行く」べきか「休ませて見守る」べきか
・「この先自分が困るよ」と言ってもよいの?
・ゲーム依存症にさせない方法
など、具体的で実行しやすい「ココロ貯金」のメソッドをお伝えします。
またメソッドだけではなく、実際にお子さんが不登校を克服したお母さんの体験記を掲載。ココロ貯金のバリエーションをご理解いただける構成になっています。
この「ココロ貯金」は本サイトで繰り返し述べている「心のエネルギー」を補給する方法と共通するものがあります。
「学校は行かなくてもいい ―親子で読みたい「正しい不登校のやり方」」 小幡和輝 著
著者の小幡和輝さんは約10年の不登校ののち、定時制高校から(正当な)“裏技”を使って国立大学に進学しました。
また、高校3年生のときに起業し、いまは学生にして社長でもあります。
そんな著者が、「学校は行かなくてもいい」という選択肢があることと、「正しい不登校のやり方」を伝えている本です。
途中にマンガを交えて著者の体験を紹介、また同じように不登校を体験しまし、今は起業している“先輩たち”の体験談(家入一真氏、吉藤オリィ氏ほか)、著者のブログに投稿された不登校経験者たちの声も多数収録しています。
本サイトでも「無理に学校に戻らなくても良い」というスタンスを取っています。
その実体験が載っていますのでぜひ参考にしてください。
「小幡和輝オフィシャルブログ | 不登校から高校生社長へ」も参考にしてください。
「子どもが不登校になっちゃった!」 ラン 著
著者のランさんは不登校コンサルタント・不登校人気ブロガーです。
28歳で起業。33歳で娘を出産。一家の収入を担うワーキングママ。
我が子が不登校になり、親としての数々の失敗を経験しました。
完全不登校脱出まで約5年かかった娘は、希望の大学に合格し、現在、大学生活を謳歌中だそうです。
自身の経験を綴ったブログでは、親子の明るい未来と人生の秘訣を伝えています。
同じように不登校の子の育て方に悩む親たちからは「納得や共感ができ、どうすれば良いのかが胸にストンと落ち、メッセージを読んでいるうちに救われた気持ちになる」と定評があります。
「不登校の親」という同じ目線で書かれていますのでご一読をおすすめします。
なお、「不登校ママから脱出した! ランのブログ」はこちらです。
アドラー心理学の本
おまけでもう一冊紹介いたします。
サイト管理者が大きな影響を受けたアドラー心理学の本です。
「超訳 アドラーの言葉」 (ディスカヴァークラシック文庫シリーズ) (エッセンシャル版ディスカヴァークラシック文庫シリーズ) 岩井俊憲 著
アドラー心理学の考え方は不登校の改善に非常に有効です。
サイト管理者は著者の岩井俊憲さんの講座を多数受講し、アドラー心理学カウンセラー養成講座も修了しています。
なお、「心のエネルギー」はアドラー心理学の「勇気」とほぼ同じ意味です。
深く学びたい方はぜひお読みください。
アクセスすべきネットの情報
ネットの情報は玉石混交です。
その中からサイト管理者がおすすめするサイトを紹介します。
キズキ共育塾の「お役立ちコラム」

キズキ共育塾とは 公式サイトより
「もう一度学び直したい方」の勉強とメンタルを完全個別指導でサポートする学習塾。
多様な生徒さんに対応(不登校・中退・引きこもりの当事者・経験者、通信制高校生・定時制高校生、勉強にブランクがある方、社会人、主婦・主夫、発達特性がある方など)。
授業内容は、小学生レベルから難関大学受験レベルまで、希望や学力などに応じて柔軟に設定可能。2024年10月現在、全国に11校とオンライン校(全国対応)。
このキズキ共育塾のサイトの中にコラム欄があり、不登校の保護者にとって参考になることが多数書かれています。
また、ここの代表の安田祐輔さんは「学校に居場所がないと感じる人のための未来が変わる勉強法」などの本も発表しています。
キズキ共育塾自体はボランティアなどではなく企業ですが、そのサイトのコラムはgoogle検索でも「不登校 親」などと検索すると、高い順位に表示される信頼あるサイトです。
東洋経済ONLINE
東洋経済ONLINEの「キャリア・教育→子育て」のカテゴリです。

書籍で紹介したランさんの記事も出ています。
不登校のお子さんを持つ保護者にも勉強になる記事が多数あります。
一般社団法人 不登校支援センター
不登校支援センターのカウンセラーブログです。
当センターは、一人でも多くのお子さんが社会に適応できるよう、2009年よりカウンセリング事業を始めました。これまでに8万人の臨床データ数を誇り、実績カウンセリング件数は累計16万件に及びます。
全国に7支部「札幌・仙台・東京・横浜・名古屋・大阪・福岡」を構え、年々増え続け、複雑化している不登校の問題の解決に取り組み、子どもたちが笑顔で復学し、社会に適応できる力をつけていくことが、私たち不登校支援センターの役目であり、使命であると考え活動してきました。
医療機関との連携、心理検査の採用など、不登校支援の正統といっても過言ではない機関です。
その施設で働くカウンセラーが書いているブログです。多くの経験から学ぶことがたくさんありますので気になるテーマがあったら読んでみてください。
不登校 親が相談すべき人
パートナー、家族
夫婦がそろっていれば、何と言ってもパートナーに相談しましょう。

相談できない事情がある場合は信頼できる家族に相談しましょう。
子どもは家族の中で暮らしています。
不登校の解決には家族の理解と協力が必ず必要です。
子どもが不登校になると家族全員が心配します。それは当然です。
しかし、その原因を考えたり、復帰のための方法や道筋に関する考え方は意外に違いがあるものです。
その違いは話し合いを通して1本化する必要があります。
一番怖いのは家族の中で「子どもが原因で諍いが起きる」ことです。
傷ついて不登校になっている子どもがますます傷ついてしまいますし、不登校が重症化することもあります。
サイト管理者の肌感では、不登校で悩んでいる方の約半分の人が、家族の問題に発展しています。
そうならないためにもこのサイトで紹介する様々な方法やサポート機関、不登校に関する学びを通して家族の結束と協力、理解を得るようにしましょう。
https://manabou-issyo.com/futoukou-oyataiou9/学校に相談する
不登校は家庭と学校の問題でもあります。
学校の先生に相談しないという方はいないでしょう。
しかし、不登校の原因を考えたときに学校への相談の仕方はそれぞれの事情によって異なってきます。
子ども自身や家庭に原因がある、と考える方は全面的に学校に協力を求めると思います。
逆に学校に原因がある、特に担任との折り合いが悪い、などという場合は学校への相談はためらわれるものですね。
しかし、だからといって相談をためらっていては全く進行はありません。
こんなときは学年主任や教頭に連絡しましょう。
詳しいやり方については下記の記事を参考にしてください。
https://manabou-issyo.com/rakkou-sennsei9/なお、このサイトでは不登校の「原因」と「きっかけ」は分けて考えています。
大切な考え方ですので、次の記事をぜひお読みください。
https://manabou-issyo.com/geninn-kikkake/その他 相談すべき人
家族、学校の他にも相談できる人はたくさんいます。
- 信頼できる友人
- 地域のカウンセラー
- ネットのオンラインカウンセリング
また、厚生労働省の公式サイト「こころもメンテしよう 若者を支えるメンタルヘルスサイト」には公的な相談窓口が掲載されています。
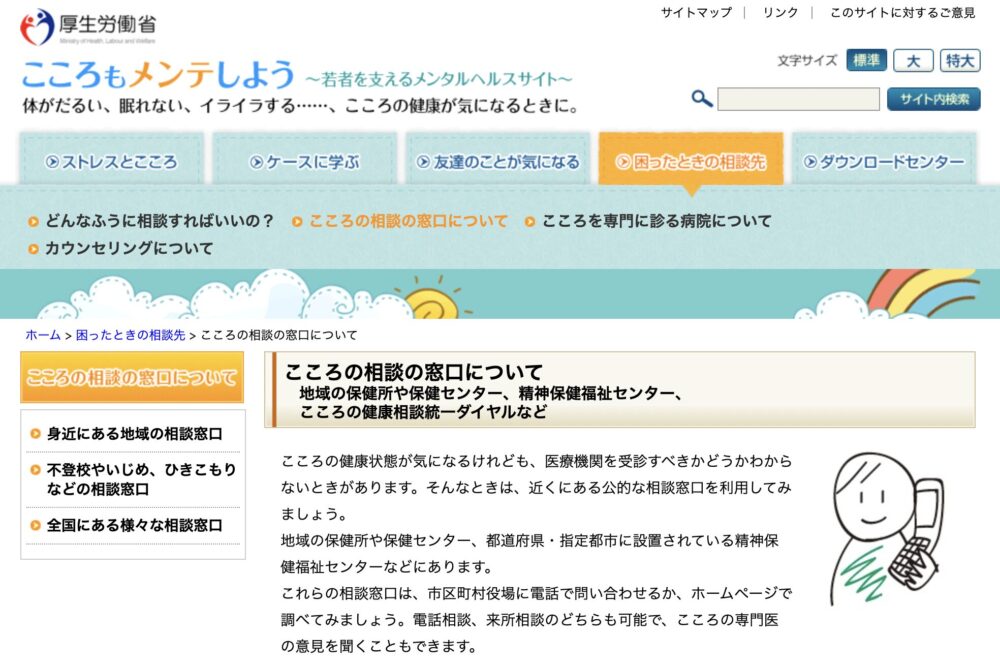
公的なもので電話がほとんどですから当然利用も無料です。最初に利用する相談窓口としてはおすすめできるところです。
ただし、ここで気をつけてほしいのは「相談」の考え方です。
「相談」=「解決」とは考えないでください。
「相談」をするときは
「話をして解決のヒントに結びつくものが一つでも得られればラッキー」
くらいの気持ちがベターです。
これに関しては「不登校かも親の対応 その8」でも解説してますので興味のある方はお読みください。
さらに言えば「相談」という行為は、相談した人が「心のエネルギー」を補給するための行為でもあります。
よく「聞いてもらっただけで楽になった」という言葉を聞きますが、まさにそのことです。
その他にも自分がお世話になっている整体師、理容師などにも相談できます。
整体師、理容師などには一種の守秘義務があります。利用者さんから聞いたプライベートな情報を他の人に話したりはしません。
そのことを知っていれば、安心して話せますね。
不登校の我が子のために一生懸命な親御さんも、ときには体と一緒に心も癒すために整体・マッサージなどを利用することをおすすめします。
不登校 訪問すべき教育機関 訪問するだけでエネルギーを補給
次に「訪問」すべき教育機関です。
この項目は大事な項目なのでしっかりとお読みください。
「相談」と何が違うのかといえば、訪問は「見学」「体験」の意味合いが大きいことです。
普段お子さんがいつも通り登校しているうちは自覚がないのですが、通常の小学生中学生が「学校」という場所に依存している割合はとても大きいものです。
この記事を読んでくださっている皆さんにはおわかりの方も多くいらっしゃると思いますが、不登校になるとそれを痛感する人が非常に多いのです。

学校に行けなくなった途端「子どもの生活に何もなくなったようになり」「将来への支えがなくなったように」不安になるのです。
今は学校が全てではありません
しかし、今は学校に変わる教育機関が多数存在します。
そのことを早い段階から知っておいていただきたのです。
学校に変わる教育機関とは具体的には次のものです。
- 自治体の教育委員会が設置している教育支援センター
- 地域のNPOなどが主催しているフリースクール
- トライ式中等部などの企業によるフリースクール
などです。
これらの施設は「十分に学校の代わりになる施設」です。
特に企業が運営するフリースクールには優秀な講師がたくさんいますので、勉強の遅れも高いレベルまで取り戻すことが十分に可能です。
お子さんを教育してくれる施設として学校しか知らない場合、学校に行けなくなったら「人生が終わった」ように感じるでしょう。
けれど、「学校だけが将来を決めるところではない。他にも代わりがたくさんある。」ということを知っていれば、親はお子さんの将来を見通すことができます。
勘違いしないでほしいのは、不登校だから教育支援センターやフリースクールに行け、と進めているのではありません。
学校に行けなくてもそれらを利用するという選択肢があるから「まだまだ大丈夫」ということを知ってほしいのです。
不登校のお子さんと親にとって、この「まだまだ大丈夫」という感覚は非常に大事です。
「学校に行けないからもう終わり」
「学校に行けない期間が長かったから、復帰しても勉強についていくことができない。だから復帰したくない。」
などと思う必要はないのです。

これを知っているだけで、親がお子さんに接するときの気持ちは随分違うはずです。
教育支援センター フリースクールとは
しかし、これら教育支援センターやフリースクールという場所は大部分の人にとって「よくわからない場所」です。
学校に通っているうちは考えもしない場所ですから当然ですね。
ですから「見学」「体験」をしてほしいのです。
もちろんお子さんも一緒に行くことができればいいのですが、親だけでも構いません。
本当に見るだけでもいいので一度足を運んでください。
さらにこの「見学」では「心のエネルギー」も補給することができます。
施設の方は快く迎えてくれますし、場合によっては簡単な相談に乗ってくれます。
なにより、不登校のお子さんが多く通う施設ですから、安心感が違います。
学校では不登校は少数派ですが、フリースクールでは多数派なので当然ですね。
とにかく関係機関を訪問するということは様々な点で大きなメリットがあります。
できるだけ早期に行動していただくことをおすすめします。
まずは電話か資料請求
なお、この訪問にあたって一番の大きなハードルは、「その施設を訪れたい」と、訪問の許可を得る一番最初の作業です。
ただの電話ですが、この最初の電話がなかなか踏み切れないのです。
サイト管理者の子どもも一時不登校だったのでその気持がよくわかります。
そんなときは、メールやホームページからの申込みを活用しましょう。
おすすめはトライ式中等部です。
下記から資料を取り寄せる操作をするだけで、その資料からトライの様子がわかりますし、連絡先を把握できます。
資料を取り寄せることによって連絡もたいへんとりすくなりますので、おすすめです。
サイト管理者も最初に利用したのがトライ式でした。
資料を取り寄せたあと、電話で様々なことを相談したことによって訪問しやすくなりました。
現地でも大変丁寧に迎えていただき、安心したことを覚えています。
そして、それによってはずみが付き、地域のフリースクールも見学することができたのです。
ちなみに「教育支援センター」は教育委員会が設置していますので、学校の先生もセンターとはつながりを持っています。
学校の先生に相談すれば、すぐに見学ができますね。
「再登校が目的」の相談機関なら 次の2つを考えよう
ここまで、不登校になったとき親がどのような行動を取ればいいのか詳しく説明してきました。
しかし、この記事を読んでくださっている方の本当の希望は「再登校」のはずです。
そんな親御さんのための相談機関を2つ紹介します。
「スダチ」と「不登校支援センター」です。
「スダチ」
「スダチ」は家庭の状況を整え、親の子どもへの接し方を具体的に伝えることで再登校に導くサポートをしています。
親御さんに子どもとの接し方を指導し
家庭での過ごし方を変えることで
間接的に再登校に導きます。
一般的な不登校支援は、支援者が直接子どもに登校を促します。
しかし、不登校のお子様は第三者と会うことを拒否して話ができないことが多いです。
スダチの支援は、親御さんに子どもとの接し方を指導し、家庭での過ごし方を変えることで間接的に再登校に導きます。→ 「スダチ」に無料相談をする

会社について
会社名 株式会社スダチ
設立 2019年5月7日
資本金 5,000,000円
代表取締役 小川涼太郎
所在地 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6丁目28番9号 東武ビル6階
社員数 95名(インターン・業務委託含む)※2024年10月時点
事業内容
- 不登校支援事業
- 子育てサポート
- スダチ式子育て塾
- 不登校診断テスト
「スダチ」は、2019年の設立以来、次のような実績を上げています。
- 累計再登校人数1,200名以上
- 再登校できたお子さん90.0%以上
- 8ヶ月以上継続登校率90.4%
また、代表取締役 小川涼太郎さんは本を著しています。
「不登校の9割は親が解決できる 3週間で再登校に導く5つのルール」
アマゾンの不登校カテゴリで1位を取っています。
「スダチ」の特徴
スダチ公式ホームページより
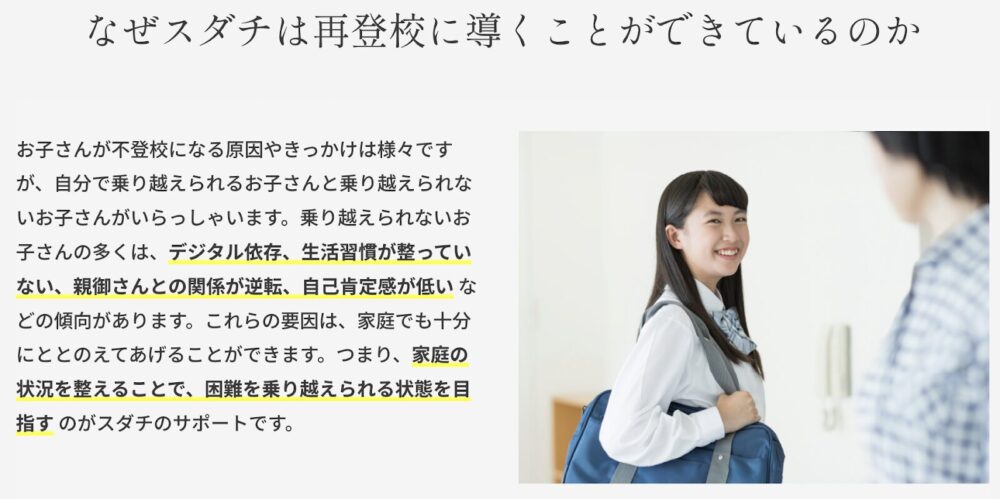
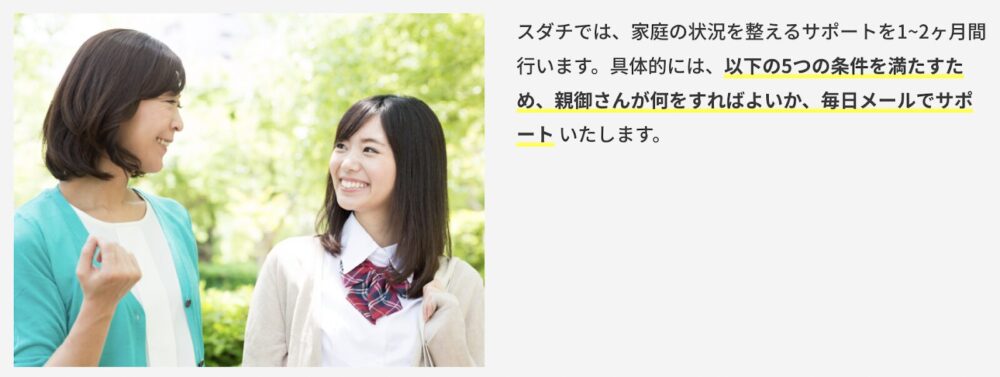
スダチ 公式サイト より
医師監修のもと、ご家庭がサポート対象か判断します
医師監修のもと、うつ症状・いじめ・家庭環境等を総合的に判断し、サポートを提供できるか判断しております。再登校が全てのお子さんにとって最善とは限らず、別の居場所が適している場合もあるため、このような基準を設けております。
ただし、多くのお子さんは身体・精神に大きな問題がなく、『何となく学校に行けない』ことに悩まれているケースが多いため、そのようなご家庭には再登校を目指したサポートを積極的に行っています
このサイトで「スダチ」をおすすめする理由
理由は「親に対して支援するから」です。
不登校を改善する最も有効な手段の一つが「親が変わる」ことです。
そのためには親自身が「心のエネルギー」を補給しなければなりません。
そのサイトではそのために
- 家族、友人への相談
- 学校への相談、地域のカウンセラーへの相談
- フリースクールなどのへの見学
を勧めています。
「スダチ」ではそれと同じ効果があることをワンストップでやってくれるのです。
しかも多くの実績を上げている「スダチ」というところが引き受けてやってくれます。
また、メールやオンラインを通じて、「毎日」サポートしてくれます。
公式ページでも書かれていますが、不登校のお子さんを抱えている方にとって最初にぶつかる大きなハードルは
子ども自身が何もしようとしない、誰と相談もしない、相談を拒否する
ということです。
子ども本人に対しての打つ手がなくなるのです。
そのときは親が何か行動をするしかありません。
本気で改善に取り組むのは親しかいないのです。
「スダチ」はそのことをよく理解しています。

当然会社ですから料金はかかります。
「スダチ」に相談したからと言って保証はありません。
しかし、不登校に疲れて家庭が疲弊していく状況から抜け出せなくなっているのならば、相談する価値は十分あります。
「スダチ」についてはこのサイトでもいずれ記事をアップする予定です。
不登校支援センター
不登校支援センターってどんなところ?
今、このHPをご覧いただいている方は、不登校のお子さんをお持ちの保護者の方か、近い関係に不登校のお子さんがいらっしゃる方かと思います。
そして「どうしたら子どもが学校に行けるようになるのだろうか」と日々悩まれているのではないでしょうか?
当センターに相談にいらっしゃるご家族の方々も皆、同じ悩みを抱えています。
では、最初に「不登校支援センター」とはどんな所か簡単に説明させていただきます
当センターは、不登校を根本から解決するための、不登校専門機関です。
お子さんが学校に通うようになるのを「ただ待つ」のではなく、学校や社会で適応していく力を身につけるために、お子さんに対して「積極的に働きかける」という手法をとっております。
全国に7支部「札幌・仙台・東京・横浜・名古屋・大阪・福岡」を構え、カウンセリングを始めとした様々な活動を通し不登校のお子さんの支援を行っております。

「不登校支援センター」 会社について
「不登校支援センター」は一般社団法人です。
「一般社団法人」という言葉はよく聞きますが、具体的には
営利を目的としない「非営利法人」であることです。
つまり、利益を上げても分配してはいけないことになっています。
「積極的な利益追求はしない団体」と捉えていただくと良いと思います。
ボランティアではありませんが、会社や個人の利益を目的としているわけでもない、ということです。
- 会長 森山 宣雄
- 理事長 吉本 奈津子
- 理事 桒原 航大
となっています。
また、各種マスコミからの取材も受けており、2024年11月にはNHKの「おはよう日本」からも取材を受けています。
それだけ、世間に認められている団体ということができるでしょう。
不登校支援センターの特徴
不登校支援センターでは、心理検査を用いて、不登校の原因を数値化しています。
例えば、コップに半分入った水を見たとき、「まだ半分ある」と思うお子さんと、「もう半分しかない」と思うお子さんでは、物事の受け止め方が違います。
当然かかるストレスも違います。
お子さんがどのような受け止め方をしているのか、それを科学的に数値やグラフで表すことで、現状を明確化することができ、より確実に不登校を解決することができます。
また、不登校支援センターでは「お子さんが動き出すのを待ちましょう」「お子さんの様子を見守りましょう」というアドバイスはしません。
「お子さんに対してどのような働きかけをするのか、また何故そのような働きかけが必要なのか」といったことを不登校専門カウンセラーが説明してくれるのです。
このサイトで不登校支援センターをおすすめする理由
「スダチ」も同じですが、確かな実績があるからです。

各地に支部がある大きな団体ということもあり、数字的には申し分ありません。
また、特徴でも紹介しましたが、不登校支援センターでは親に対して具体的なアドバイスをしてくれます。
具体的な働きかけの方法とその理由などを専門のカウンセラーが説明してくれます。
つまり、この施設でも親に対して「心のエネルギー」を補給してくれるのです。
そして「スダチ」と大きく違うところは
お子さんに対して「積極的に働きかける」という手法をとっているところです。
子ども本人にもはたらきかけをするのです。
親御さんの中にはぜひ子どもと直接話してほしい、と切望する方もいらっしゃいます。
そのような方には一度足を運んでいただきたい施設です
オンラインでの相談も受け付けていますので、全国の方が利用できる施設です。
不登校の子と親が目指す「自立」とは
このサイトでは
不登校の子と親が目指すゴールを「自立」としています。
自立の具体的な姿は様々な定義が考えられますが、
このサイトでは次の4つを掲げています。
- 友人がいる
- 職場の人と会話ができるコミュニケーション力
- 最低賃金で週40時間働くことができる気持ちと体力
- FP3級を取得できる学力
これらは今不登校になっているお子さんを抱えている方々にとっては手が届かないものと映るかもしれません。
しかし、本気で不登校に向き合い、お子さんの幸せを願う親の方にはぜひ目指してほしいゴールです。

サイト管理者も様々な不登校に関する情報に接してきましたが、このような自立のゴールを設定しているところは見当たりませんでした。
おそらく、いま不登校で悩んでいる子と親にとっては「それどころではない」からだと思います。
また、ネットの情報では「あるある」ですが、自社の宣伝に誘導する記事が多いので、高すぎる目標を設定するとお客がよってこない、というリアルな事情もあります。
なお、このサイトでもPR記事は書いていますが、本当に役に立つ、とサイト管理者が考えているからです。
特にトライ式については「どんなお子さんにも対応できる、一番柔軟で万能な第三の教育機関」として紹介しています。
話がそれてしまいましたが、
- 友人がいる
- 職場の人と会話ができるコミュニケーション力
- 最低賃金で週40時間働くことができる気持ちと体力
- FP3級を取得できる学力
のそれぞれの姿についてはきちんと理由があります。
今後詳しい記事をアップしていきますので、いずれお読みいただければ幸いです。
ただ、ここで知っていただきたいことは
これらの力を今すぐつけろ、というのではない、ということです。
ひとつの目安として22歳つまり大学を卒業する年齢を設定しています。
中学校1年生のお子さんであれば10年あります。
10年という時間の中でじっくり取り組もう、と考えていただきたいのです。
ちなみに、この「自立の姿」はすべてのお子さんが身につけるべき姿だと考えています。
ただ、「学校」というレールに乗っていると自覚しないままそこに連れて行かれているだけです。
そういう意味では「不登校の経験は社会で生きていく本当の意味を学ぶ貴重な機会」と考えることができます。
不登校の親と子のための「生きる力と進路の学習」
不登校になっても目指すゴールとその道筋がわかれば勇気を持って行動することができます。
このサイトではその道筋を水先案内人として指し示します。
それが「生きる力と進路の学習」です。
親子と家族が「心のエネルギー」を補給しながら学校に頼らない生き方を探っていく進路学習です。
不登校のお子さんの学びの場は驚くほど多様化している
生きる力と進路の学習では
- 親は、先に述べた相談先・施設をフル活用し、自分自身の心のエネルギーを補給します。
- 不登校克服のための自分のネットワークを構築します。
- 子ども自身が心のエネルギーを補給し、活動を再開したとき提供できる「学びの場」を常に準備します。
- 子どもが活動を再開したら、親子ともに心のエネルギーを補給しながらその道を進みます。
- 選んだ道はいつでも変更が可能です。柔軟に考えましょう。
- 3年、5年、10年というスパンの中で子どもの変化を確認しましょう。確実に成長しているはずです。
「学びの場」は学校に戻るという選択肢かもしれませんし、フリースクールなどの第三者の機関かもしれません。
子ども自身が行ってみたい、自分が幸せになるために行動したい、と思える教育施設に行くようにしましょう。
それをできるだけ多く提供できるように親は準備すべきです。
準備を進めていく中で、親も様々な学びと気づきがあります。
https://manabou-issyo.com/supportschool-towa/ https://manabou-issyo.com/kanzen-supportkouerabi/中学校時代のフリースクールはもちろん、高校進学にあたっても通信制高校や各種サポート校など不登校のお子さんの学びの場は驚くほど多様化しているのです。
その現実を受け入れ、自分の子どもがその選択肢を選ぼうとしたときの心の準備が必要です。
例えば高校進学にあたってお子さんが「通信制高校とサポート校を選ぶ」ことを選択したとき、親自身が「全日制高校への進学が絶対である」という価値観を持っていれば子どもは苦しんでしまうからです。
現代の学校は本当に苦しんでまで通うべきところなのか
このサイトでは現代の「学校」についても考察しています。
率直に申し上げれば、「今の学校は苦しんでまで通うべきところなのか。」
ということです。

サイト管理者の正直な意見として「学校はオワコン」だと思っています。
したがって学校に戻りたくなければ、違う道を探すことがベターな行動だと考えています。
考えてみてください。
- 学校が苦しいけれど、学校に戻らなければならない、だけど体が動かない、といって悩み続ける生活。
- 学校でないけど、この施設なら行ける、といって、その施設に通う生活
後者の方が子どもにとって良い生活なのは明白です。
苦しんでまで学校に行く必要はないのです。
繰り返しますが、学校だけが将来に結びつく教育施設ではないのです。
高校進学を機に全日制高校に進学 休まず登校した例はたくさんある
サイト管理者は数々の生徒を目の前で見てきました。
毎年100人程度の卒業生を送り出す生活を30年続けました。
合計3000人以上の進路を見つめてきたことになります。
不登校のお子さんを持つ家庭もたくさん見てきました。
その中に、お子さんに「心のエネルギー」を注ぎ込み続けたご家庭がありました。
サイト管理者を含め担当の教師も子どもとそのご家庭に「勇気」という「心のエネルギー」を注ぎ込み続けました。
すると、その家庭の子どもたちは、高校進学を機に全日制高校に通い始めたのです。
しかも「ほとんど休まずに3年間登校しました」と報告してくださる保護者の方も少なからずいるのです。
サイト管理者も最初は信じられませんでしたが、これらは珍しいケースではないのです。
家庭訪問をしても一度も会うことができなかった子どもがほぼ無欠席で全日制高校に登校したという例もありました。
実は、これと同じことが、高校から大学に進学する場合にも起こります。
つまり、高校でも不登校を克服できず、通信制高校やサポート校を選んだお子さんでも、大学進学を機に友達と一緒の大学に通い始めるのです。
または、就職して周囲の社会人と何ら変わることなく社会生活を送ることができるのです。

もちろん子ども本人の努力が大きいことは言うまでもありません。
しかし、その子どもに「努力できる環境」を提供したことも含め、周囲の人たちが子どもの底力を信じ、根気強く長い時間をかけて「心のエネルギー」を注ぎ続けた結果なのです。
「心のエネルギー」はじっくり時間をかけることでしか充填されません。
不登校になり、様々な手立てをとってようやく再登校できたのに、また不登校になってしまったという事例をよく聞きます。
それは「心のエネルギー」が十分に溜まっていないにもかかわらず登校してしまったためです。
「見せかけの元気」では学校というストレスの塊のような場所に耐えられないのです。
不登校の子へ「親」としての接し方
親であるとはどういうことでしょう。
このサイトでは次のように考えています。
- 子どもへの影響力がずば抜けて大きい存在
- 「生きるいうことの手本」を見せ続ける存在
- 「生きるための考え方」を示す存在
- 見返りを要求しない「子どもにとっての応援団」
- いつでも「助け舟」を出す準備ができているカウンセラー
- 自立するまでの期間経済的支援をする存在
親が親である期間はとても短いものです。長くても22年、実質的には15年前後ではないでしょうか。
そして、その期間以上に親であろうとすれば、逆に子どもにとっては悪影響となります。
言葉通り「子ども扱い」をしてしまうからです。
保証を手厚くするほど要求は強くなる
「保証を手厚くするほど、要求は強くなる」
という言葉があります。
モンスターペアレントはこの典型です。
サイト管理者の考えですが、モンスターペアレントとは、
「学校は子どもの成長を保証する場所である。子どもが成長できないのは学校のせい、子どもが辛い思いをしているのは学校が悪い。」
と考えている人たちです。
その結果として、子どもになにかあったとき「どうしてくれるのだ」と学校にねじ込んでくるのです。
どうして突然モンスターペアレントの話などするかといえば、
「不登校のお子さんの親御さんは、知らず知らずのうちに、自分自身が自分自身に対してのモンスターペアレントになってしまうときがあるから。」
です。

つまり、自分だけが子どもを幸せにできる、幸せにしなければならない、という十字架を背負ってしまうのです。
そして、不登校から抜け出せない場合、子どもを幸せにできない自分を責めることになるのです。
そうなってはいけません。
https://manabou-issyo.com/futoko-geninjibun/子どもは自分自身で成長し 困難を乗り越え 人生を切り拓いていくもの
子どもは自分自身で成長し、困難を乗り越え、人生を切り拓いていくものです。
親や教師ができるのはその手助けだけです。
あるいは「いくつかの先例」を指し示すだけです。
この考え方を踏まえてもう一度「親であるとは」の前3つを見てください。
- 子どもへの影響力がずば抜けて大きい存在
- 「生きるいうことの手本」を見せ続ける存在
- 「生きるための考え方」を示す存在
この3つは実はほぼ同じことを言っています。
親は子どもをコントロールできません。
ただ、他の人より「影響力が大きい」だけです。「親の言うことをきいている」のではなく、影響を大きく受けているだけなのです。
その影響のうち最も大きいものは言葉ではありません。「親の生き方そのもの」であり、「親の考え方そのもの」です。
子どもは物心付く前から「親の生き方」と「親の考え方」に深く接しています。
自分の周囲にいる大人は実質、親だけです。
子ども自身は影響を受けているという自覚はありませんが、いつの間にか「生き方」「考え方」が似通ってしまうのです。

ですから、親は子どもをコントロールしているのではありません。
子どもも「なんとなく親の言うことに従っている」と思っていますが、それは
「親の提案が自分にとって受け入れやすいものが多い」
だけなのです。
これらのことは子どもの不登校を考えるうえで大事な事なので、いずれ別記事で書きたいと思います。
親は応援団でありカウンセラーである
後半の3つは言葉のとおりです。
- 見返りを要求しない「子どもにとっての応援団」
- いつでも助け舟を出す準備ができているカウンセラー
- 自立するまでの期間 経済的支援をする存在
特に大事なのは2の「いつでも助け舟を出す準備ができているカウンセラー」です。
子どもは自分の問題を自分で解決しなければなりません。
親が解決してあげるのは「過保護」です。
ただし、子どもは子どもであり、いわば「発展途上人」です。
子どもは、問題を解決する術や方法をきちんと知らないことがあります。
自分自身では困っているけど、その困っている本質を見ることができない場合もありますね。
例えば宿題が終わらないから学校に行きたくない、という場合、問題の本質は「宿題をすることができなかった自分」にあります。
その場合親は
- 宿題をするための時間の確保の仕方
- 宿題に取り組むマインド
- 宿題の内容が難しい場合は一緒に考えてあげる
などの案をお子さんに提示すべきなのです。
そしてそれらの案を子ども自身が検討して、自分にあっている方法を「採用」し、実行するようにしていくのです。
カウンセラーとは「問題を解決する人」ではありません。
「本人が問題を解決するために歩みをともにする人」です。
ですから、宿題が終わらなかったからと言って親が代わりに宿題をやってあげるのはNGなのです。
アドラー心理学では「課題の分離」という
少々むずかしい話になってしまいましたが、アドラー心理学では「課題の分離」といい、そのものズバリの言葉で説明しています。

アドラー心理学の「課題の分離」は次のように説明できます。
- 自分のことは自分でやる。人のことは人にまかせる。
- 子どもの宿題を親が代理ですることはしない。手伝ったり、解き方を教えることはあっても。
- 人の問題を解決しようとしすぎず、応援する気持ちを持つ。
- 不登校は究極的には「子ども自身の課題」であり、「子どもが自分の責任で解決すべきもの」
- 子どもが解決の方向を探り、子ども自身が解決したいと思うことが大事。そのための応援やエネルギー、勇気、簡単な手助けを与え続けよう。
くわしくは「不登校は親の責任か 正しい「原因自分論」で不登校を乗り越えよう」 を御覧ください。
自分の子どもは課題を解決する力がどの程度あるか
紹介した「課題の分離」を正確に実行するためには
親は「自分の子どもの現在の課題解決の力」を見極めなければなりません。
- 課題そのものに立ち向かう気力つまり、「心のエネルギー」はどの程度あるか
- 言葉としてどの程度自分の気持を表現することができるか。
- 自分の中で感情を処理するタイプか、外に向かって立ち向かうタイプか。
- 課題の本質を正確に捉えているか。
- 課題そのものを解決する技術や方法をどの程度知っているか。
極端な例ですが、いじめを受けた小学校1年生の子どもに「自分でなんとかしなさい」とは言えません。
その技術も方法も「自分の気持ちを表す言葉」すらも持ち合わせていないからです。
「辛かったね」
「それでも頑張って勉強してきて偉かったね」
「大丈夫お父さんがついているから」
なんなら、「一緒にやっつけに行こうか」などの冗談も交えながら、そういった友達への対応の仕方を教えたり、先生に相談したりする必要があるでしょう。

代理で解決することはしませんが、問題解決能力が低い場合、親の「手助け」の度合いは高くなるわけです。
さらに、子どもとの対話の時間も長く必要、というところも大事でしょう。
手助けそのものに時間がかかるということはもちろんですが。
「親は自分のために時間を割いてくれている」
「親は自分のためにいつでも応援してくれている」
という感覚こそが大切だからです。
これらのことによって問題解決能力を徐々に高めていき「自分で解決できて偉いね」となり、
年齢が進んで最終的には「自分で解決できて頼もしくなったね」
とならなければなりません。
どんな子どもでもコミュニケーションに喜びを感じる
この記事の最後に
どんな子どもでもコミュニケーションに喜びを感じる
ということを紹介します。
「どんな子どもでもコミュニケーションに喜びを感じる」は
サイト管理者が30年以上中学校に勤務し、現在も子どもと関わる仕事を続ける中で間違いない、と感じることの一つです。
自閉症で一般的に対人関係が苦手、といわれる子どもでも、人とのコミュニケーションに喜びを感じています。
それは「対人関係をつくることが苦手」なだけであって、
「コミュニケーションそのもので得ることのできる喜び」は私達と一緒なのです。
これはすべての子どもに共通しています。
子どもだけではありません、どんな大人もそうです。
それまでの人生でたくさん傷つけられ、もう人とは話したくない、と思っている大人でも温かいコミュニケーションを心の底から求めています。
誤解を恐れずに言えば、そのコミュニケーションとは「愛」と呼ばれるものに言い換えることができます。

どんな人間でも自分をわかってくれる人、自分の味方が必要です。
だいそれたことを要求してるのではありません。
些細なことでいいのです。
誰かが自分と一緒に他愛のない話をして、笑い合ってくれるだけでいいのです。
不登校の子どもも同じです。
引きこもってしまっていても同じです。
子どもの「幸せになりたい」という気持ちを理解し「愛」という「心のエネルギー」を私たち親は送り続けなければならないのです。