子どもが不登校になると、多くの親御さんが「自分が原因では?」と悩むことがあります。
ですが、家庭に虐待やネグレクトなどの深刻な問題がない限り、「不登校の原因が親にある」ということは絶対にありません。
 Kon
Konそれでも、中学校教員を30年以上やってきた私の経験を振り返ると、「共通する傾向として」子どもが不登校になりやすい親の特徴、というものを感じたことも確かです。
そこで今回は、その特徴を7つお話しします。
この記事を読めば、子どもが不登校になりやすい親の特徴や傾向を知ることができます。また、そのような親がどんなタイプの性格なのか、それを改善するためのヒントも解説しています。
誤解しないでいただきたいのですが、これからご紹介する特徴は、親として誰もが持っているものであり、特別なものではありません。
また、これらが不登校の決定的な要因ではありません。
それぞれの子どもを取り巻く環境や状況の中で、たまたま「不登校という状態」に結びついてしまっただけなのです。
そこをご理解いただき、どうか安心して読み進めていただければと思います。
不登校の子どもを持つ親に見られる特徴7つ


特徴①:完璧主義的な考えを持っている
完璧主義的な考えを持っている親御さんは、実は自分自身にも厳しい人です。
そして、もしかしたら、親御さん自身が上司や家族から「完璧を求められている人」かもしれません。
🔷 親が取りがちな行動の具体例
- 子どもの結果を重視しすぎる
テストで90点を取ってきても「次はもっと良い点を取ろう」と言ってしまう。 - 失敗を許さない雰囲気を作る
「どうしてこんなことができなかったの?」と責める。 - 子どもの成果に過剰に干渉する
宿題や自分の趣味で取り組んでいるものについて親が口を出してやり直させたり、完璧に仕上げさせる。
🔻 子どもが受け取るマイナスのメッセージ
- 「失敗は許されない」
- 「親に認められるには完璧でなければならない」
- 「自分はダメな子だ」



親としては向上心を促すつもりの言葉でも、子どもにとっては「今のままでは足りないのだ」とプレッシャーを感じさせる結果になることがあるんです。
🔸改善のヒント
- 子どもの努力を評価する
結果ではなく、取り組む姿勢や過程を褒めることを心がけましょう。 - 失敗を受け入れる
子どもが失敗したときには、「これも成長の一部だよ」と声をかけましょう。 - 親自身の完璧主義を手放す
親も完璧である必要はありません。時には失敗を共有することで、子どもに安心感を与えます。



学校で話を聞くとわかるのですが、どんな子どもでも「親の期待に応えたい」と思っています。「高すぎる期待」は子どもの心のエネルギーを奪う結果になるのです。
特徴②:子どもを第一に考えすぎる
子どもを最優先に考える親の姿勢は素晴らしいものです。子どもの幸せを心の底から願っている親御さんです。
しかし、もしかしたら親御さん自身は「自分は両親から十分な愛情を受けることができなかった」と感じている方かもしれません。
🔹 親が取りがちな行動の具体例
- 子どもの意見を最優先にする
家族の予定や食事のメニューなど、すべてを子どもの希望に合わせる。 - 自分の時間を犠牲にする
親自身の趣味や友人との時間をすべて子どもに使う。 - 子どもの失敗を避けようとする
子どもが挑戦する前に「無理しなくていいよ」と止めてしまう。
🔻 子どもが受け取るマイナスのメッセージ
- 「自分が親をコントロールしてしまっているようで怖い」
- 「親に負担や迷惑をかけているかもしれない」
- 「自分の失敗は親に恥をかかせる結果になるかもしれない」



これらのメッセージは子どもにとって、過剰な責任感を持たせたり、自信を失わせる要因となることがあるんです。
🔸 改善のヒント
- 家族全体のバランスを意識する
子どもの意見を大切にしながら、家族全体のバランスを考えましょう。 - 親自身の時間を大切にする
親が楽しむ姿を見せることで、子どもは「自分も自分の時間を楽しんでいいんだ」と感じます。 - 子どもの挑戦を応援する
子どもが失敗しても、「大丈夫、次があるよ」と安心させる声掛けを心がけましょう。



子どもは、特に中学生になれば「親の苦労」に敏感になるものです。言葉で言うことは滅多にありませんけどね。
特徴③:子どもを放置気味である
子どもを放置しがちな親御さんは結構いるものです。「自分も一人でやってきた」「子どもは自分で考えている」など理由は様々なようです。
しかしこのような親御さんは、もしかしたら、忙しくて自分にゆとりがないことをそのような言葉で言い訳しているのかもしれません。
🔹 親が取りがちな行動の具体例
- 子どもの話を聞かない
子どもが話しかけても「後で」「忙しい」といった言葉で流してしまう。 - 関心を持たない
子どもの学校生活や友人関係に興味を示さない。 - 時間を共有しない
一緒に過ごす時間がほとんどなく、家族としての交流が少ない。
🔻 子どもが受け取るマイナスのメッセージ
- 「自分は親にとって大切ではない」
- 「何をしても親は気にしない」
- 「自分には価値がない」



これらのメッセージは子どもにとって、自分自身を大切にする気持ちが薄くなったり、学校や友だちとの関係にも不安を抱くようになったりする要因になることがあるんです。
🔸 改善のヒント
- 子どもの話を聞く
忙しくても子どもの話に耳を傾け、「それでどう思ったの?」と質問することで関心を示しましょう。 - 一緒に過ごす時間を作る
食事や遊びの時間を共有し、子どもとの絆を深めることが大切です。一緒に散歩をするだけでもいいでしょう。 - 子どもの変化に気づく
子どもの小さな変化やサインに注意を払い、「最近どう?」と気軽に声をかけましょう。 - 自分の生活を見直す
親自身が抱えるストレスや忙しさを整理し、子どもとの時間を優先できるよう工夫しましょう。



「もう中学生なんだから自分でやれって言ってるんだ」とおっしゃる親御さんは意外に多くいます。それはときどき「放置」になっちゃんですよね・・・。
特徴④:子育ては母親のみに任せっきり


この特徴の親御さん(この場合はお父さんですが)は「子どもを放置気味である」とほぼ同じことが言えます。
⚠️ しかし、次のことに注意してください。
- お父さんが子どもに関心がない場合、お母さんが頑張るほど子どもはお父さんの無関心が見えてしまう。
- お母さんがお父さんに必要以上に気を使ったり、お父さんがお母さんを責める場面を目撃したりすると、子どもの精神的負担は大きくなる。



子どもにとって「お母さん」という存在は理屈抜きで特別なものです。



そのお母さんが大変な姿を見てしまうということは、子どもにとって影響は非常に大きいのです。とくに夫婦のトラブルの原因が子ども自身であると感じた場合、子どもの心には大きな影が落ちてしまうものです。
特徴⑤:「自分もできたから、子どももできるはず」と考える
親が「自分もできたから、子どももできるはず」と考えるのは自然なことです。
しかし、もしかしたらこのような親御さんは、人一倍努力して今の職業や地位を勝ち取ってきた方なのかもしれません。
🔹 親が取りがちな行動の具体例
- 感謝や褒める言葉を省いてしまう。
子どもが努力しても、「これくらいは当然」と言ってしまう - 過去の自分と子供を比べる
「私がこの年齢のときにはもっと頑張っていた」という。 - 現在の自分の視点で物事を言う
「100点を取れなかったの?私だったらこんな間違いはしない」と言ってしまう。



これらの行動をとってしまう親は、子どもにとって「ウザい親」になることがあり、子どもとの信頼関係を損なう可能性があるのです。
🔻 子どもが受け取るマイナスのメッセージ
- 「親は自分を認めてくれない」
- 「どんなに頑張っても、親は満足しない」
- 「結局、自分は親とは違う」
🔸 改善のヒント
- 比較をやめる
他人や過去の自分と比べるのではなく、子ども自身の成長や進歩に注目しましょう。 - 子どもの気持ちに寄り添う
「今、どう感じているの?」と子どもの心に耳を傾けることで、信頼関係が深まります。 - 親自身の価値観を見直す
「こうあるべき」という固定観念を手放し、子どもの個性を尊重することを意識しましょう。



親が子どもに自身の成功体験を語って聞かせる、ということは「あなたもできるから同じことをしなさい」とプレッシャーを掛けてしまうことでもあります。
これを「同一視」といいますが、多くの場合この同一視は良い結果を生みません。(※)
※ プラスに働く同一視もあります。同一視がいつも悪いわけではありません。
特徴⑥:過干渉である
過干渉とは子どもの生活の細部にまで関与しすぎてしまうことです。
しかし、もしかしたらこのタイプの親御さんは、親御さん自身が「家族や会社の上司から自分が管理されている」人なのかもしれません。
🔹 親が取りがちな行動の具体例
- 子どもの予定をすべて管理する
習い事や勉強のスケジュールを親がすべて決めてしまう。 - 子どもの行動に逐一口出しする
服の選び方や宿題の進め方など、細かいことまで指示を出す。 - 子どもの人間関係に介入する
「この子とは遊ばない方がいい」と友だち関係に干渉する。
🔻 子どもが受け取るマイナスのメッセージ
- 「自分では何もできない」
- 「親がいないと困る」
- 「自分の意見は尊重されない」



これらのメッセージは、子どもの自立心を妨げる要因となることがあります。
🔸 改善のヒント
- 子どもに自己決定の機会を与える
習い事や日々の予定について、子ども自身に選ばせる場面を増やしましょう。 - 子どもの意見を尊重する
「どうしたいの?」と子どもの気持ちを聞き、それを反映する努力をしましょう。 - 見守る姿勢を大切にする
困ったときにはサポートしつつも、基本的には子どもを信じて見守ることが重要です。



妙にオドオドしている生徒に出会うことがあります。
自分の行動を自分で決定できないのです。自分の行動を親に依存してしまうんですね。
特徴⑦:過保護である
過保護とは子どもがしなければならないことを先回りをして親がやってしまうことです。
このようなタイプの親御さんは、もしかしたら非常に優秀で職場や家族の人から頼りにされている人かもしれません。そして気持ちが優しいため困っている人を見ると助けてやりたくなるタイプの方です。
🔹 親が取りがちな行動の具体例
- 子どもの感情を過度に守る
子どもが直面する問題に対して、「心配だから」と親が先回りして対応する。
また、子どもが悲しい思いをしないように、友達とのトラブルや困難な状況を親がすぐに解決しようとする。 - 子どもの選択肢を制限する
「これが一番いいから」と子どもが選ぶ前に親が決定してしまう。 - 子どもの代理をする
宿題が終わっていない子どもの代わりに親が宿題をしてしまう。
🔻 子どもが受け取るマイナスのメッセージ
- 「自分は何もしなくてよい」
- 「挑戦することは危険だ」
- 「困難なことは親が自分の代わりにするべきだ」



これらのメッセージは、子どもから独立心を奪ってしまうことがあります。稀に、問題が生じたとき親がやってくれないとわかると、怒りだすこともあるんです。
🔸 改善のヒント
- 挑戦の機会を提供する
子どもが自分で解決する時間を与え、「困ったら手伝うよ」と安心させる。 - 小さな失敗を許容する
子どもを見守り、失敗しても「これも経験だね」と受け入れ、次に活かす姿勢を伝える。 - 子どもの自立を信じる
子どもが自分で考え、行動する力を尊重し、少しずつ手を引いて見守る。
過保護と過干渉はよく似ていますが、招く悪い結果は全く違います。
過干渉が招く悪い結果は「不安で自信がなく、自分では何も挑戦できない子ども」で
それに対して過保護が招く悪い結果は「傲慢で自分を過大に評価する子ども」です。



いわゆる「嘘つく子ども」に過保護タイプが多いように思います。
本当は親がしているのに自分ができるように思ってしまったり、友達にもそのように伝えてしまうのです。
親の心身の健康が子どもに与える3つの影響とは?


親が笑顔でいるだけで、子どもは安心感を覚えます。
親自身の心身が健康だと、子どもに良い影響を与えるのです。
この章では、子どもに与える具体的な「3つの良い影響」を解説します。
影響①:子どもの安心感が高まる
親が穏やかで安定した態度を示すことで、子どもは「この家は安全な場所だ」と感じます。
親の心身が健康であれば、子どもに対して余裕を持って話を聞いたり、共感したりすることができ、子どもは「自分の問題を話しても大丈夫」と思いやすくなります。



いつ話をしても包容力があふれている親御さんがいます。そのお子さん達は、プレッシャーにも強く元気もあるようです。
影響②:子どもの自己肯定感が高まる
自己肯定感を育てる一番の早道は、親が子どもに「ありがとう」をたくさん言うことです。
自己肯定感とは「自分には意味がある」「自分の存在は大切だ」と自分で思える感覚です。
心身にゆとりがある親は、「ありがとう」をたくさん使えます。



私が出会った優秀な教師のみなさんも、「ありがとう」の使い方が非常に上手でしたよ。
影響③:子どもの課題解決能力が育まれる
課題解決能力が身につく方法の一つは「たくさん失敗すること」です。
たくさん失敗するためには「失敗しても許される環境」が必要です。
心身が健康ならば、親は「おおらかなに見守る」ことができます。



子どもは好奇心の塊です。環境さえ整えば、「実戦」で知識やスキルが身につくのです。
不登校に向き合う親へのエール:「自分らしく」が一番


子どもが不登校になったとき、親は「もっと頑張らなければ」「自分がしっかりしなければ」と自分を追い詰めてしまいがちです。
しかし親の姿に「正解」というものはありません。
不完全でも、家族を大切にし、親ができる範囲で「自分らしく」向き合えば、それだけで子どもにとっては大きな支えになります。
この章では、親が肩の力を抜きながら子どもに向き合うための心構えをお伝えします。
心構え① 「親として完璧でなくてもいい」と認める
親自身が「不完全な自分」を受け入れ気持ちが楽になると、子どものことも受け入れることができるようになります。
当然ですが、親でも子どもでも完璧である必要はないのです。
いつも笑顔でいたい、いつも子どもに優しくたい、家事を上手にこなしたい、親ならば誰しもが望むことですよね。
けれどそんな完璧な親はいません。



「完璧である」ことより、「なりたい自分に向かって努力する」ことが大切ですし現実的です。
私が出会った子どもたちの中にも、努力している親御さんのことを嬉しそうに報告してくる生徒がたくさんいました。
心構え② 親自身も助けを求める勇気を持つ
今の世の中で「相談できる」ということは重要なスキルです。
「問題を抱えてしまう」となかなか相談できないのが現実ですが、そこを乗り越える勇気を持ちましょう。
相談先はたくさんあります。
学校、教育支援センター、フリースクール、カウンセリングセンター、オンライン相談、自治体の子どもダイヤル・相談ダイヤル、不登校の子どもを持つ親の会、家庭教師、etc
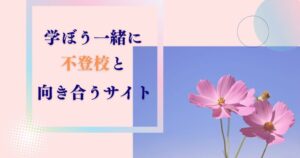
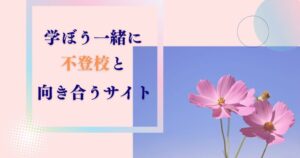



教育支援センターは各自治体の教育委員会が設置しているところが大部分です。学校に頼めばすぐに繋いでもらえますよ。
心構え③ 子どもと一緒に「今」を大切にする
未来のことを心配しすぎず、子どもと一緒に「今」を大切にすることを心がけましょう。
先のことばかり考えて焦ると、目の前の子どもの小さな変化や気持ちに気づけなくなります。
例えば、子どもと一緒に料理をしたり、散歩を楽しんだりといった何気ない日常を共有することで、子どもとの絆が深まります。
「高校進学が心配だけど、今は子どもが笑顔でいられることを大切にしよう」と考えることで、家庭内の雰囲気も穏やかになります。



不登校のお子さんをお持ちの親御さんにとって、「笑顔で今を大切にしろ」と言われても難しいですよ。



私も子どもが不登校だったのでよくわかります。けれど、親ができる最良の方法は「親の一番ステキなところを子どもに示し続ける」ことだと思います。



矛盾しているようですが「子どもは自分のせいで親が元気がない」と思うとショックを受けるものなんです・・。
よくある質問とその回答
- 子どもが学校に行きたくないと言ったとき、親はどう対応すればいいですか?
-
まず、子どもの気持ちを否定せず、子どもが安心して話せる雰囲気を作ることが大切です。学校に行けない理由がすぐに分からない場合でも焦らずに、信頼関係を築くことを最優先にしてください。
- 不登校が長引くと進学や就職に影響しますか?
-
進学や就職の道は必ずしも学校に通うことだけではありません。通信制高校やフリースクールなど、柔軟な選択肢が増えています。不登校の期間があったとしても、その経験を生かして成功している例はたくさんありますので、焦らずにお子さんに合った方法を探しましょう。
- 子どもが家で何もせず過ごしているのですが、大丈夫でしょうか?
-
一見すると何もしていないように見えても、子どもは休養を必要としている場合があります。この時間は心と体を整えるための大切な期間です。無理に何かをさせるのではなく、好きなことを見つけるきっかけを提供したり、温かく見守ることが重要です。
- 親同士で情報交換することは有益ですか?
-
同じような経験を持つ親と情報交換することは大いに役立ちます。他の家庭の対応方法を知ることで、自分の状況を客観的に見ることができたり、新しいアプローチが見つかることもあります。ただし、他人と自分を比較して自分を責めないように注意が必要です。
- 子どもが部屋に引きこもるのをやめさせる方法はありますか?
-
無理に引きこもりをやめさせようとするのではなく、子どもが少しずつ外に目を向けるきっかけを作ることが重要です。例えば、部屋の外で好きな食べ物を用意したり、簡単な仕事を頼んだりすることも有効です。子どもが自然な形で出てくる状態を作ることが大切です。
- 不登校の子どもに家で勉強させるべきですか?
-
不登校の状況にある子どもに無理に勉強をさせる必要はありません。心の安定を取り戻すことが優先です。ただし、子どもが学習に興味を示した場合は、通信教育や動画教材など柔軟な方法でサポートするのが良いでしょう。
- 不登校が家族全体に与える影響をどう乗り越えればいいですか?
-
不登校は親だけでなく、兄弟姉妹にも影響を与えることがあります。家庭内でオープンに話し合い、全員が安心できる環境を整えることが大切です。親自身が冷静に状況を受け止めることで、家族全体が協力しやすくなります。
ここで上げた回答は一例に過ぎません。不登校は複合的な要因がありますので、参考程度に考えてください。
この記事のまとめ


- 不登校の子どもを持つ親には共通の特徴があり、完璧主義や過干渉などの行動が子どもに影響を与えるときがあるが、それが原因ではない。不登校は複合的な要因で誰もがなる可能性がある。
- 親の心身の健康状態は、子どもの安心感や自己肯定感に大きく影響するため、親自身のリフレッシュやストレス管理が非常に重要。
- 他の親と比較せず、自分たち家族に合った対応を見つけることが、不登校解決への第一歩。大きな変化を求めず、小さな変化を積み重ねる姿勢が大事。
- 学校との連携や教育支援センター、フリースクールなど外部のサポートを積極的に活用することで、親と子どもに新たな選択肢が生まれる。
- 子どもと共に「今」を大切にする姿勢が、家庭全体の雰囲気を明るくし、不登校の改善につながることが多い。
フリースクールについてはトライ式を推薦しています。
理由は「どんなお子さんにも対応できる、一番柔軟で万能な第三の教育機関」だからです。よろしければ、こちらの記事をお読みください。
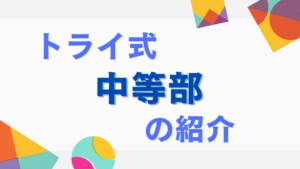
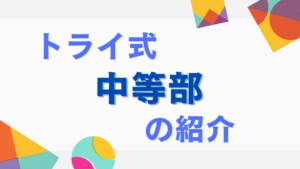
親御さんだけの見学や相談も可能です。



私も一人で見学に行きました。
子どものためにできることの「小さな一歩」だったと思っています。
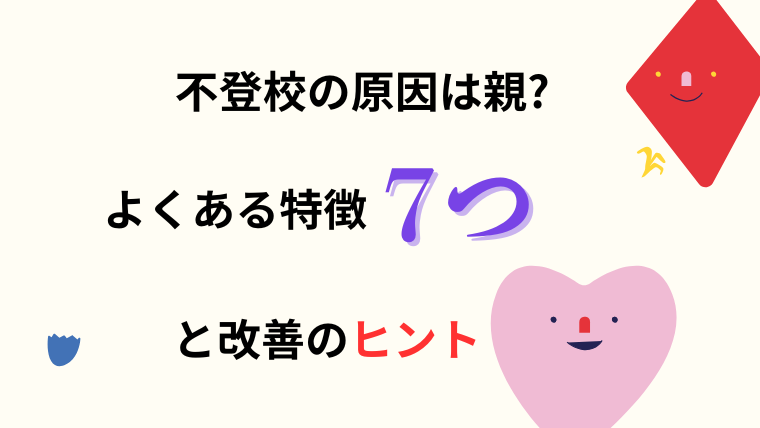
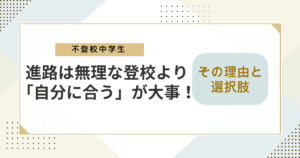
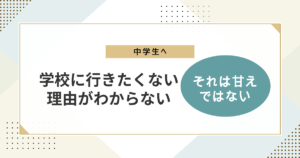
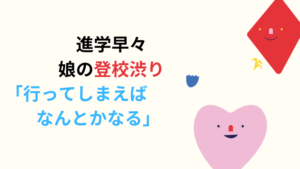
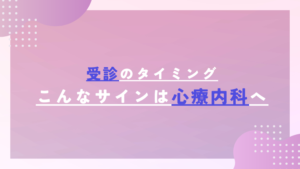

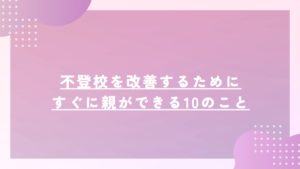

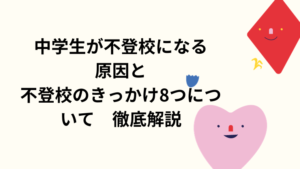
コメント