2025年5月NHKの午後6時からの「Nらじ」を車の運転しながら聞いていたら、興味深い方が出演なさっていました。
小沢ちえさん、ほのさんの親子です。
聞けば、親子でカウンセリング活動をしているとのこと。
不登校の子どもさん本人は娘のほのさんが
保護者はお母さんのちえさんが担当なさっているということでした。
 Kon
Konサイト管理者のkonとしては、運転を間違いそうになるくらい「目からウロコ」でした。
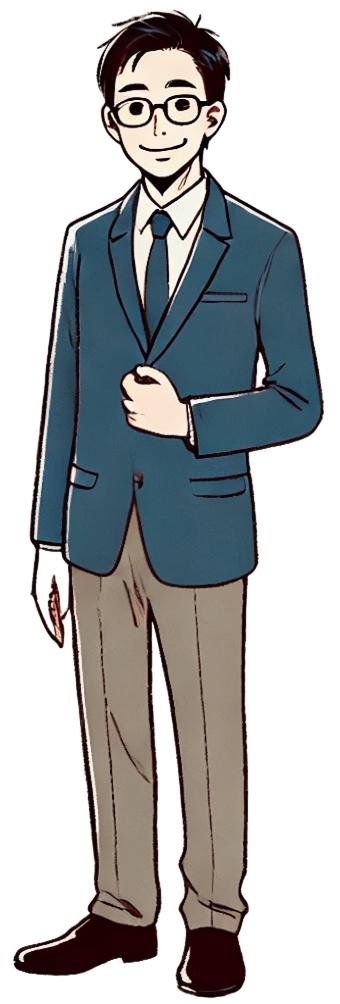
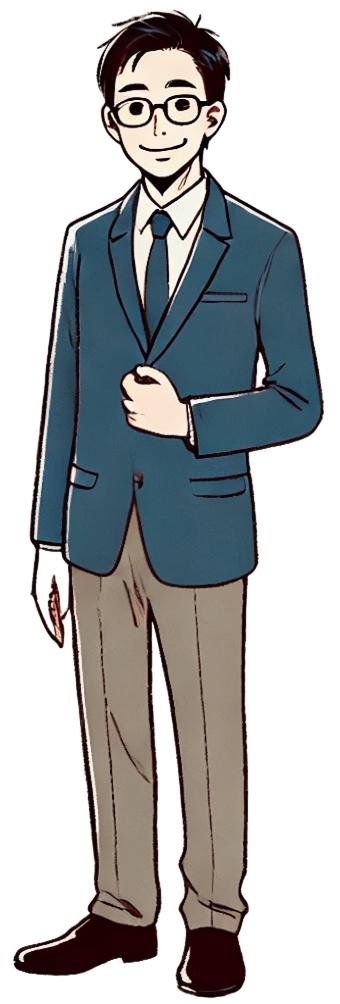
- もと中学校の教員 35年間勤務
- アドラー心理学、認知行動療法、コーチングなどを学ぶ
- 「子どもに一生懸命でない保護者はいない」が信条
- 現在も教育関係の仕事に従事
- 自分の子どもが2人とも不登校を経験。
- その経験から不登校についての発信を始める。
普通、不登校のカウンセリングは子どもが受けたがらないものです。
ですから我々は「まずは保護者の方がカウンセリングを受けてください」ということが多くなります。
しかし、「カウンセラーの娘」が「不登校生徒の話を聞く」とは。
びっくりすると同時に「きっと効果がある」と思って聞きました。
以下、小沢さん親子の会話をピックアップしながら内容を解説していきます。
- 不登校の親子には「親と子を分けて話を聞く」カウンセリングが効果的で、安心して本音を話せる環境が信頼関係を築きます。
- 子どもはゲームやアニメなどの共通点から心を開きやすく、親が教えられる姿勢になることで距離が縮まります。
- 質問攻めは逆効果であり、子どもがポロッと話すのを待ち、その言葉を否定せずに受け止めることが信頼を深めます。
- 親は子どもの進路や行動を決めつけず、自分の価値観を見直し「子ども自身が考える力」を信じることが大切です。
- 祖父母の価値観が関係を難しくすることもあり、親がその板挟みになる現実を理解し、家庭内の対話環境を整える必要があります。
「じぶんらしさ商店」とは?──不登校の親子に寄り添うカウンセリング


不登校の子どもを前に、親として「どう接すればいいのか」「誰に相談すればいいのか」と悩みを抱える方は少なくありません。
そんな中、NHKラジオ『Nらじ』に登場し、多くの親の共感を集めたのが、小沢ちえさんと娘・ほのさんによる「じぶんらしさ商店」の親子カウンセリングです。
■ Nらじで語られた「当事者としてのはじまり」
小沢ちえさんは、「最初は私自身が不登校の娘をどうしたらいいかわからなかった」と語ります。



つまり娘の 小沢ほのさん が不登校だったのです。
「娘が不登校だった時、お友達から“うちの子も不登校なんだけど、ちえちゃんと娘ちゃん一緒に来てくれない?”って言われたのがきっかけでした。」
「最初は不安でしたけど、娘がそのお子さんとアニメやYouTubeの話をして打ち解けていくのを見て、“これならいけるかも”って思ったんです。」
この体験が、「不登校の親子が、親子のままで他の親子を支える」という独自のカウンセリングの出発点でした。



活動の原点は「自分たちも困っていた」というリアルな出発点にあります。だからこそ、悩んでいる親子に“寄り添う力”が生まれたようです。
■ 親と子、それぞれが話しやすい相手に
カウンセリングでは、親と子を分けて話を聞く形式をとっています。
「相談者の親は私が担当し、子どもには娘のほのがつきます。お互いが一番話しやすい相手と向き合えるようにしているんです。」
「私は親御さんとお茶をしながら“ママ友”のように話します。娘はゲームをしたりアニメの話をしたりして、お子さんと自然に心の距離を縮めていきます。」
親子別々に45分ずつ話を聞いたあと、最後の45分で親子が再び向き合い、それぞれの気持ちを伝え合う時間を設けています。



子どもにとって見れば「自分と同じ不登校の人」というのは何よりの味方ですよね。
■ ゲーム・アニメ・YouTube ── 共通点が心を開く扉に


娘のほのさんは、自分がかつて学校に行けなくなった経験を活かし、子どもたちに寄り添っています。
「ゲームしたり、YouTube見たり、好きなアニメの話をしたり。そこから“あ、この人、自分と似てるかも”って思ってもらえると、自然と会話が生まれます。」
「私自身も、アニメの話をきっかけに母と仲良くなれました。“おすすめのアニメある?”って聞いてくれたことが嬉しかったんです。」
この「同じ目線で話す」姿勢が、子どもたちと話ができるポイントのようです。



子どもとの対話は「正論」はうまくいかないんですよね。「共通点」があるのは強みですね。
なぜ「親子別々に話す」カウンセリングが効果的なのか?
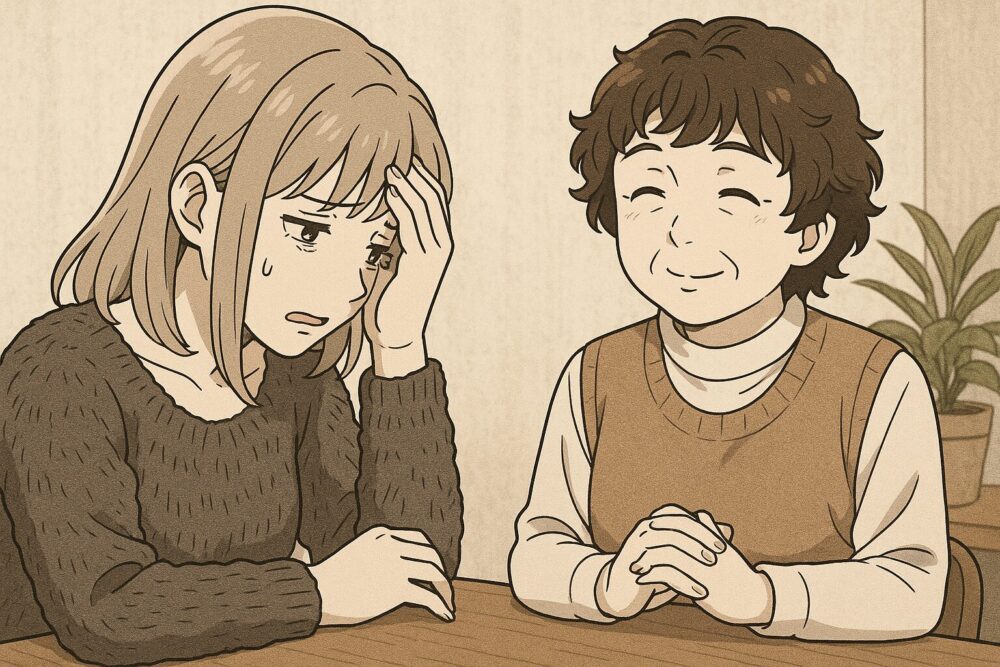
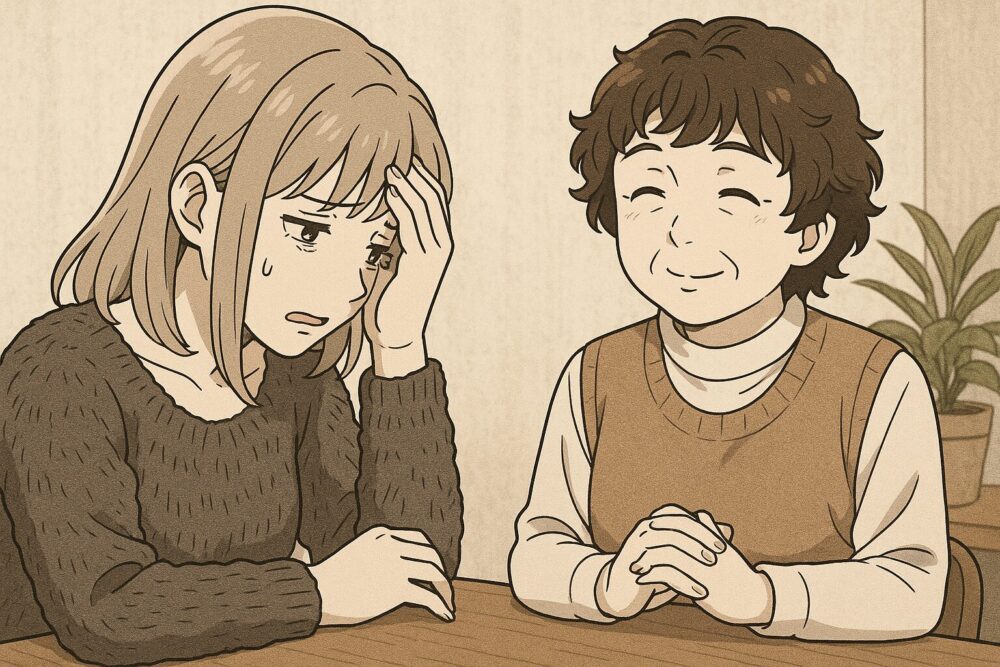
不登校の子どもを持つ親が陥りがちなのが、「子どもと話したいのに、うまく話せない」「聞いても答えてくれない」という悩みです。
小沢さん親子が実践する“親と子を分けて話を聞く”というスタイルには、親子の心をほぐす大切な意味が込められています。Nらじで語られた言葉の中からそれを探ってみましょう。
■ 「子どもは、同世代の誰かと話したかっただけかもしれない」
小沢ちえさんは、娘・ほのさんの役割について、こう語ります。
「娘のほのは、相談者のお子さんと一緒にゲームをしたり、アニメの話をしたりして、自然と仲良くなるんです。」
「子どもたちは、学校に行っていない分、同じような経験をした誰かと話したかったんだと思うんです。」
ほのさんが“話す”のではなく、“一緒に過ごす”ことから始めるのは、相手のペースに合わせるための配慮です。



専門家ではなく「少し先を歩いた同世代」が聞き手になっていることが貴重ですね。
■ 「親の言葉が届かないときは、第三者が“橋渡し”になる」
子どもに直接話しても伝わらない、あるいは反発されてしまう――そんなときこそ、「第三者の存在」が大きな意味を持ちます。
ちえさんは話します。
「親の言葉だと反発してしまうことも、ほのが代わりに伝えると、すんなり受け取ってもらえることがあるんです。」
「同じように、私が子どもから聞いたことを親御さんに伝えると、“そういう気持ちだったんだ”と冷静に受け止められることもあります。」
小沢さん親子は、感情的になりやすい親子間のコミュニケーションを、冷静に整える“通訳”のような役割があるわけです。



第三者が間に入ることで、親子の本音が“翻訳”され、届くべき形で相手に伝わるようになります。
■ 「質問攻めではなく、子どもが話すのを“待つ”」
親の多くがやりがちな行動に「どうして行けないの?」「理由は?」と質問を重ねることがあります。
それが逆効果になることを、小沢さんは身をもって知りました。



このサイトでも同様のことを書いています。


「“学校行けないの?”って毎日聞いていたら、ケンカになってしまって…」
「でも子どもって、おやつのときとか、夕飯のときとか、ふとした瞬間に“実はさ…”って話すんです。」
「その“ポロッと話したこと”を聞いてあげて、ちゃんと受け止めてあげることが大事なんです。」
言葉を引き出すには、“問い詰める”のではなく、“待つ”ことが何より大切だといいます。



子どもが話す瞬間は、親の都合ではなく私達の心の準備ができたときです。
小沢さん親子の体験談から学ぶ、親の向き合い方と子どもの気持ち


子どもが不登校になると、親としての戸惑いや不安、焦りは計り知れません。
小沢さんも最初は「学校に行かないなんてありえない」と思っていたと語ります。
そこから少しずつ、親子で向き合い、関係を修復してきた体験がありました。
■ 「私は学校に行かないなんて、ありえないと思っていた」
不登校になった娘を前に、小沢さんは最初、受け入れられなかったと率直に語ります。
「私はもう“学校に行かないなんてありえない”って思ってました。」
「どこにも相談できなくて、“私の育て方が悪かったのかも”ってずっと自分を責めていました。」
「毎朝“今日学校行くの?”って聞いて、でもそれが結局、ケンカの原因になってしまっていたんです。」
この言葉には、多くの親が共感できるのではないでしょうか。



親の不安が先に立つと、子どもの気持ちは見えなくなりがちです。
■ 「話したくなかった。部屋で一人で将来のことばかり考えてた」
今ではイラストレーターとして活動しているほのさんです。
娘のほのさんは、母との関係についてこう振り返ります。
「自分の気持ちは、ほとんど言わなかったです。」
「“学校どうするの?”って聞かれるのがすごくつらくて、部屋に引きこもってました。」
「でもそのとき、ただ遊んでるわけじゃなくて、将来やりたいことを調べたり、どうしたらいいかずっと考えてました。」
「何もしていないように見える子どもたちも、実は内面ではいろんなことを考えている」という現実。それを、親はつい見落としてしまいます。



子どもは“黙っている”のではなく、“言葉にできない思い”を抱えています。
■ 「アニメを教えてって言ったら、初めて娘と笑い合えた」
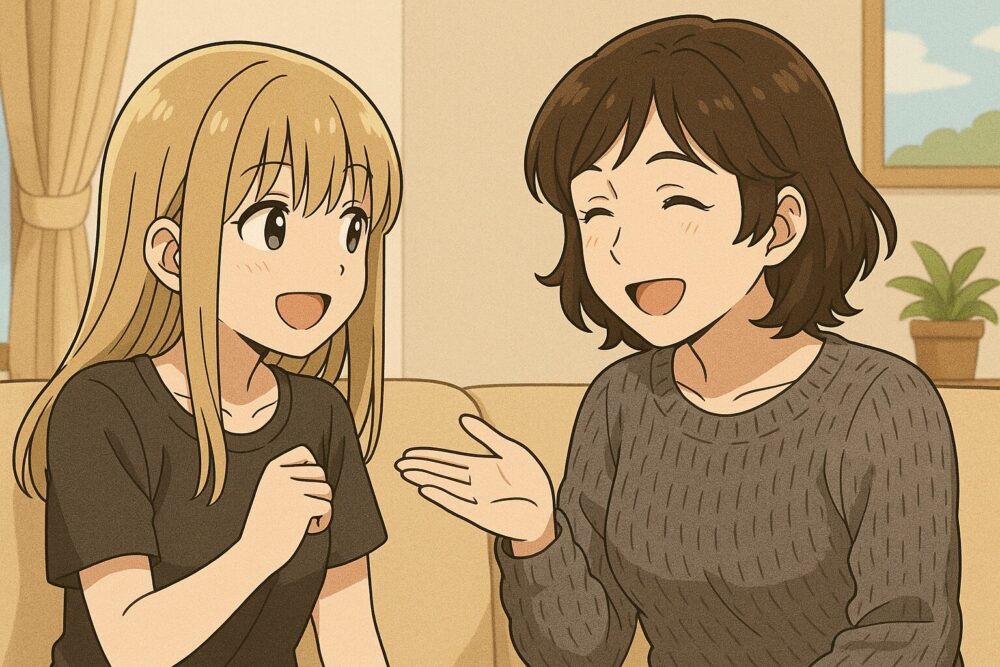
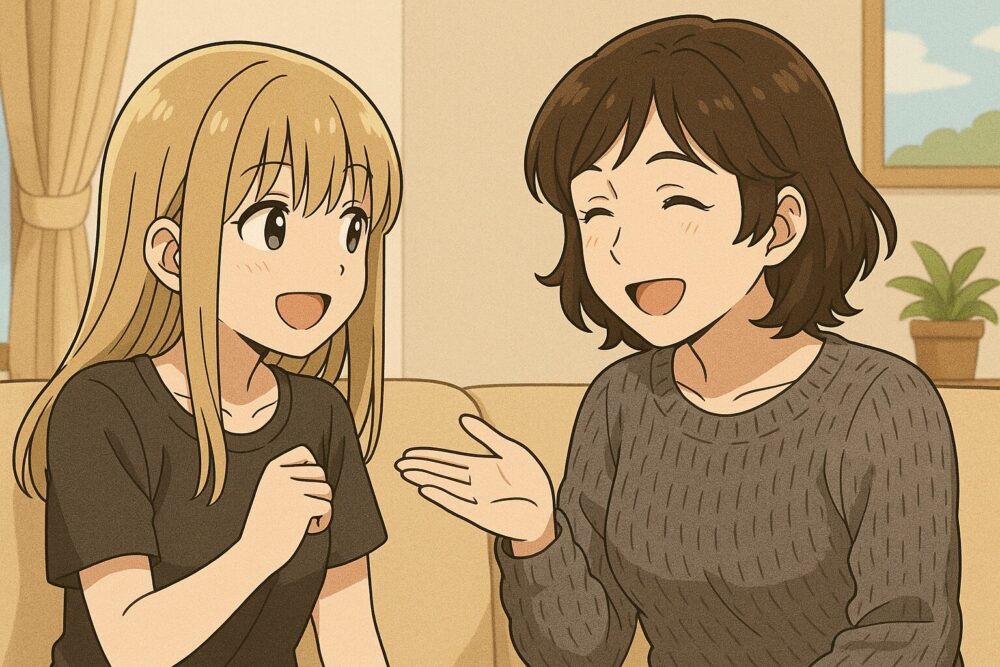
親子関係が少しずつ変わっていったのは、ほんの些細なきっかけからでした。
ちえさんは話します
「私もアニメが好きで、“おすすめのアニメ教えてよ”って言ったら、そこで娘がすごく楽しそうに話してくれて。」
「それまでは喧嘩ばっかりだったけど、ようやく“普通の会話”ができたんです。」
「ああ、この子は、学校の話はできなくても、好きなことなら話せるんだって気づきました。」
そこから、少しずつ親子の距離が縮まり、気持ちを交わせるようになったといいます。



「子どもに教えてもらう」という姿勢が、信頼関係をつくったわけです。親が“(いつも)上から”では子どもは話しにくいものです。
不登校支援で直面する「祖父母の壁」とその乗り越え方
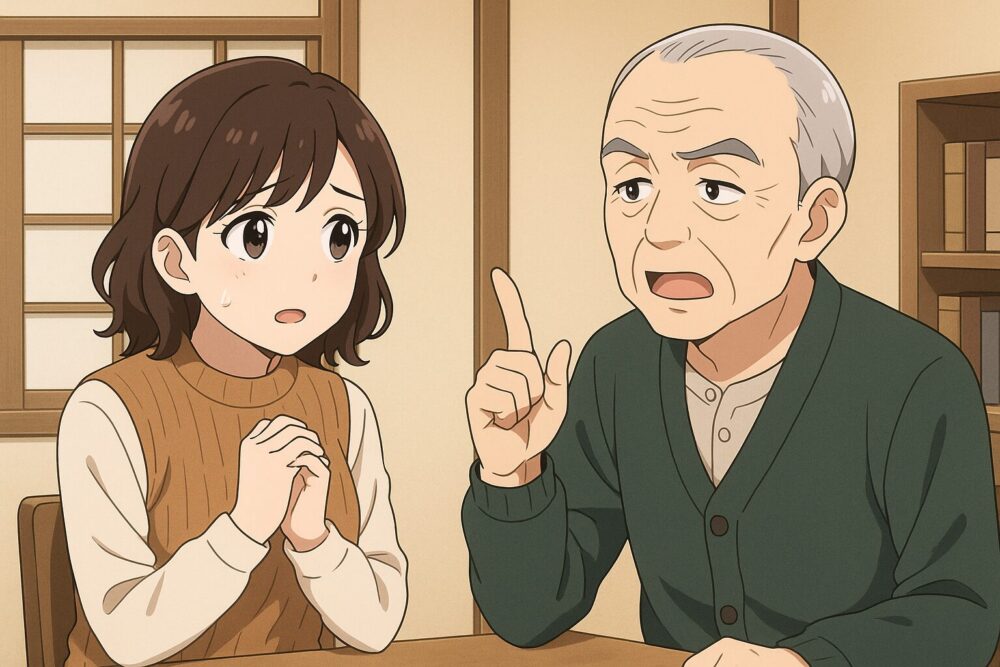
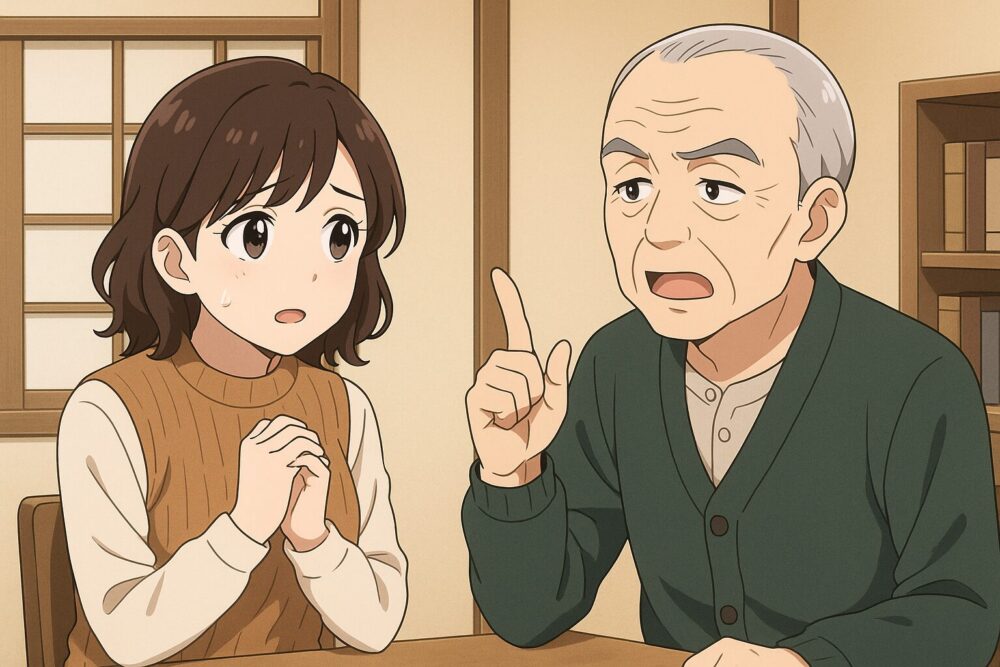
不登校の問題に直面したとき、家族の中で最初に支援に立ち上がるのは、多くの場合“親”です。
しかし、意外と見落とされがちなのが「祖父母の存在」です。
小沢さんは、祖父母が関与する家庭のカウンセリングには“独特の難しさ”があると語っています。



このサイトでも「不登校になったとき、同居家族に祖父母がいる場合、協力してもらう」ということを書いています。


見えにくいけれど、確実に影響を与えている「三世代の関係性」に注目してみましょう。
■ 「おじいちゃんおばあちゃんが出てくると、ちょっと難しくなる」
小沢さんが、カウンセリングの中で特に「難しいぞ」と感じるケースのひとつが、祖父母が前面に出てくる家庭です。
「やっぱり、おじいちゃんおばあちゃんが出てくると、ちょっと難しいですね。」
「どうしても“いい学校入ればいい会社入れる”っていう昭和の価値観が強くて。」
「そういう価値観を押しつけられると、子どもは本当に潰れてしまうんです。」
これは決して祖父母を責める話ではなく、「時代背景の違い」が子どもに負荷をかけてしまうという現実を、丁寧に伝えている言葉です。



おじいちゃん、おばあちゃんにとっては「善意」で言っているのですが、価値観の世代差は子どもにとって重圧になり得ます。
親世代が間に立ち、翻訳し、バランスを取ることが必要です。
■ 「親もまた、祖父母との板挟みに苦しんでいる」
小沢さんは、祖父母からのプレッシャーを受ける親自身が、実は最も苦しんでいるとも語ります。
「お父さんお母さんたちも、やっぱりおじいちゃんおばあちゃんに遠慮があるんですよね。」
「“ちゃんと学校行かせなきゃ”“将来どうするんだ”って言われると、自分の考えに自信が持てなくなってしまう。」
「だからまず、親御さん自身のカウンセリングが必要になることもあるんです。」



子どものサポートの前に、親の心の土台を整える必要がある、ということです。
■ 「昭和の正解が、今の子どもにとっての正解とは限らない」
小沢さんは、「古い価値観」を頭ごなしに否定するのではなく、「今は時代が変わっている」という事実を丁寧に伝えようとしています。
「私も親として、最初は“学校行かないなんてダメ”って思ってました。でも、それが本当にその子のためだったのか、今は違う視点で見られるようになりました。」
「不登校でも、明るい未来がある。そう信じてもらえたら、子どもも前を向けると思うんです。」



親も祖父母も、「正しさ」より「柔らかさ」を。時代の変化を受け入れる姿勢が大切です。


考え方をシフトする


ちょっとした“考え方のシフト”が、子どもとの関係を大きく変えるきっかけになります。
■ 親の価値観をアップデートする
小沢さんが何度も語っていたのが「親自身の考えを見直す」ということです。
「私は、子どもに選択をさせていませんでした。安心してほしいから、“そっちの道にしておいたほうがいいよ”って言ってたんです。」
「でも、それって親の“安心”のためであって、子どものためじゃなかったって気づいたんです。」
「不登校でも、ちゃんと将来はある。そのことを、親が一番に信じてあげてほしいです。」
“良かれと思って”の声かけが、子どもを追い詰めてしまうこともある。
「正しい道に導く」のではなく、「その子の道を応援する」へ。親の意識が変わると、子どもは自然と動き出します。



このサイトでも「親は子どもの応援団」ということに触れています。
■ 「子どもの声を、奪わないでほしい」
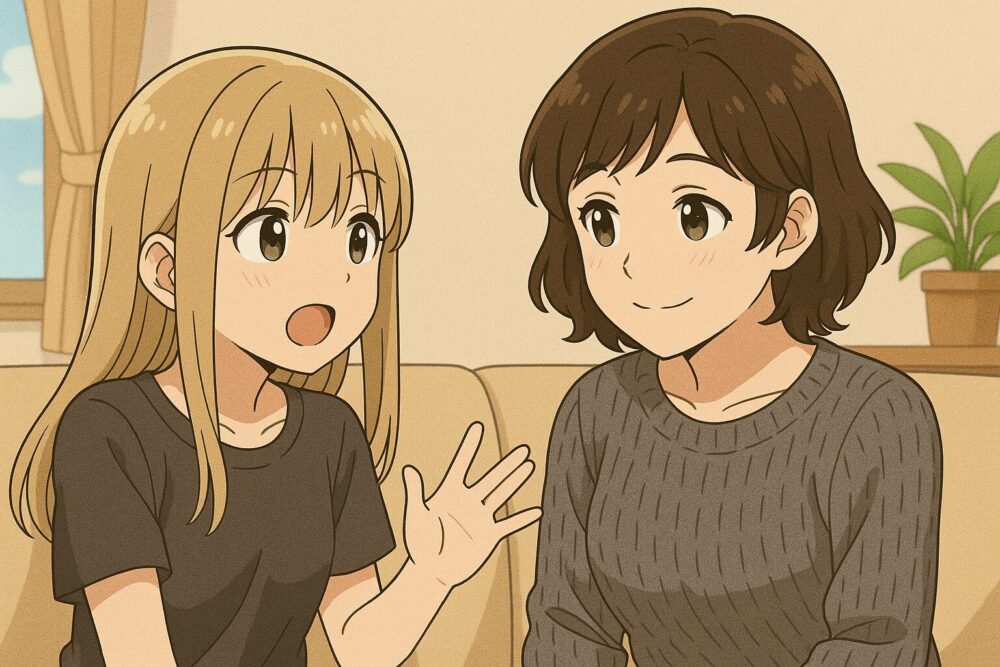
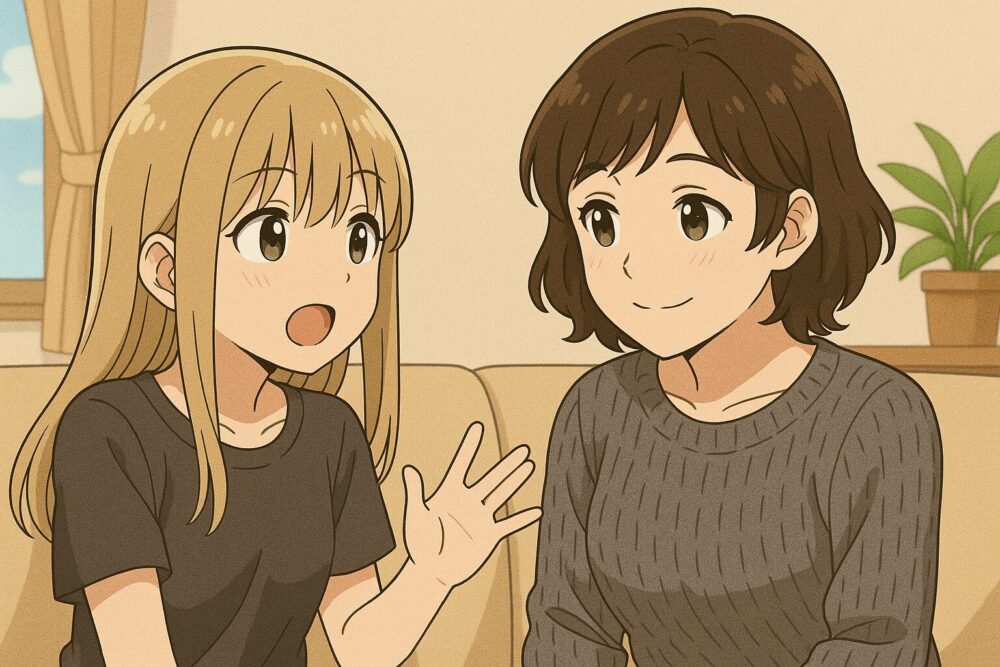
小沢ちえさんが強調したのは、親が“良かれと思って”子どもの代わりに決めてしまう危うさでした。
「私も昔は“こうした方がいいよ”って、子どもの選択を先に決めちゃってました。」
「でも、それって結局は親の安心のためで、子どもにとっては重荷だったんですよね。」
「不登校から抜け出すには、子ども自身が“自分で考えられる”って思えることが本当に大事なんです。」
“こうすべき”ではなく、“どうしたい?”を問いかける。
それが、子どもに「自分の人生」を取り戻させる第一歩になります。
現代は情報が溢れ、価値観が多様化しています。
「親の導き」という感覚は過去のものです。親が現代の感覚についていくことは難しくなってきています。



中学校で進路を選ぶときも「必ず子どもが決めてください」と言っていました。
「親のアドバイス」はあったとしても「決定」は子どもにしてもらうのです。
「子どもの選択を支える」という考え方のほうがこれからの時代にあっていると思います。
まとめ
- 小沢さんのフェイスブック「砂時計カウンセリング じぶんらしさ商店」のリンクです。
- シチズン・オブ・ザ・イヤー2024 受賞者紹介「小沢ちえさん」へのリンクです。
この記事を書くにあたってNらじの内容をまとめたり、NotebookLMで情報を整理したりしました。その下書きの全文を掲載しておきます。興味のある方はお読みください。
(右の三角印▼をタップすると開きます)
ただし、形式は下書きのままで整っていません。誤字脱字名前の表記違いなどもありますがご容赦ください。
みんなのニュースです。杉田さん。
はい。今日はですね、子供たちの不登校について考えたいと思います。
毎年大型連休明けには増加するとも指摘されていますよね。
はい。文部科学省によりますと、 2023 年度の小中学生の不投校児童生徒数は 34 万人を超え過去最多となっているそうです。
はい。今日はですね、自分たちの当事者としての経験を生かしまして 不登校に悩む親子それぞれに話を聞く親子カウンセリングという活動をご紹介します。
はい。私は名古屋市を中心に活動する親子母親の小沢ちえさん、娘の小沢のほのさんです。
それではよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
お願いします。
今親子で不登校のご相談に乗っているということですけれども、どんな様子なんですか?
はい。え、私たちあのカウンセリングの時に親とこですね、別れて話を 聞くんですけれども
はい。はい。
ま、相談者の親は私が聞きまして、
相手のお子さんのお話は、ま、娘のほのが相談を聞くというスタイルになっているんですね。
ああ。
その時に親としては、ま、ま、マ友のような感じで話をしてくれるのが 1 番話しやすいかなと思っているので。
はい。はい。
そんなスタイルで 2 人でお茶しながら話をしたりとか。
うん。
で、娘のほのは相談者のお子さんとゲームをしたり、アニメのお話をしたりとか。
ああ。 あと例えば動画 YouTube ですね。そんなのを見たりとかしてうん。
そっから、ま、共通点を見つけたり、その中でほのがうまいこと相手さんの心を開いてもらうっていう。
うん。
で、ま、それを 45 分ずつ行まして、
その後の 45 分は子供さんからの気持ちを通して私たちに伝える。
うん。
親としての気持ちは、ま、私だったり相手の相談者の親御さんが伝えるっていう。で、そこでうまく お互いの意見を伝え合ってもらって
うん。うん。
どうやってやったらこの今の環境を
少しでも軽くすることができるのかっていう
うん。
ま、解決の糸口を見つけるっていうタイルですね。
はい。
はい。
ちえさんとほさんが立ち合って親子の対話を中立ちするようなそんなイメージですかね。
うん。あ、そうです。そうです。
うん。なるほど。でもどうしてそのようなこうスタイルの相談を受け付けようっていうきっかけっていうのはどういうことだったんでしょうか?
はい。あの、私の本当 になるんですけれども、さん、私の娘不登校だから
うん。
ほのちゃんと一緒にうちに来てっていうのが言われたことがきっかけで
はい。
で、その当時その娘さん中学校 2 年生だったんですね。
うん。
どうしようかなと思ってで、まと相談をして
ええ、
ま、でもやっぱり不登校の子の話を聞いてあげたいっていう気持ちが強かったので、
じゃあ、ま、一度お家にお邪魔しようっていうことになりまして。
ええ、
で、その時はもうほのが娘さんと話して 私はお友達と一緒に話をして
うん。うん。
で、話をしていくうちに、ま、色々やっぱり親は親で色々考えることがある。子供は子供でその、ま、そこの家が募家庭だったので
高校進学することを悩んでいて、学費の面とか自分がやりたいことがあって、そういう学校に行きたいけれども行けないんじゃないかとか
うん。
いろんな複雑な思いだったり、やっぱり友達関係のことで悩んだりしていたことがあったので
うん。
そこをま、ほのが YouTube 見たりアニメの話をしたん して彼女の心をまほぐしていって
うん。
で、話を聞いたってもう本当にそこなんですね、きっかけが。
あ、ほのさんはそのご自身の投稿の経験が今の相談に役立っているということだと思うんですけれども、どんなご経験だったんですか?
えっと、中学入って間もない時に学校の先生からうん。はい。
整理がひどかったんで。
うん。
チュアブルの薬を舐めたりしたら怒られたりとか。
うん。ああ。薬を飲んでいたら怒られた。はい。
うん。飴。 んだろうとか
ああ、
あとは体調がやっぱり優れなかったのでトイレに休み時間から次の授業
うん。 1
時間分をトイレで過ごしていたら
うん。
授業を
うん。
サボってるみたいな感じで言われて
しまって学校に行くのをやめちゃいましたね。
うん。ああ。それがきっかけになって学校に行く気持ちがなくなってしまった。
そうですね。
うん。ちえさんはその状況をどのように受け止めていたんですか?
私はもう学校に 行かないっていうのがちょっとありえないと思っていて
うん。
はい。
で、学校に行かないこともそもそも受け入れられないし。
ただ相談する場所がどこにもなかったんですね。
うん。ああ。
どうしようって思で 1 番は私の育て方がやっぱり間違っていたんじゃないかとか。
うん。
で、どうやってやったらまずあの子が学校に行くんだろうっていう毎日連れの戦いですよね。
うん。
で、毎日朝今日学校行くのをどうするのっていうので声をかければ喧嘩になりますしうん。 うん。
ただこの先どうなるんだろう。高校新学とかも
本当にろんなことが心配になって不安になって
うん。
とにかくほのと一緒にいるようにはしたんですけども
うん。
ほさんはそういうお母さんの様子を見ていて
はい。
自分の気持ちはお母さんには言えたんですか?それともやっぱり言いにくかった?
自分の気持ちはもうほとんど言わなかったです。
うん。
うん。
やっぱママからなんか怒られたりとか か学校どうするのって聞かれるのとかがすごいやっぱりその時は辛くて
はい。
で、家にいる時はもう基本部屋に引きこもってずっと将来やりたいことを考えたりして色々自分で調べたりとか
そういうことしてたのでまだうん
1人でいる時が 1 番楽でした。
それでお母さん娘さんと向き合うということになってその状況っていうのはどうだったんですか?
どうやって解決したらいいんだろうって本当にそれしかなくって
うん。
じゃあ今何が この子にできるんだろうっていうところで
はい。
私アニメが元々好きなので
うん。うん。
で、ま、うちの娘にちっちゃいとから本当にアニメをたくさん見せていたので
うん。
そこの繋がりで
私もアニメをもう 1 回見たいから
なんかほののおすめなアニメ教えてくれるって私も見るよっていうのから本当に仲良くなって
あ、会話がそこから始まった。
そうですね。そこですね。
へえ。
で、そっから今こういうおすすめなアニメもあるよとか、お母さんこういうのもいいよとか。
うん。そう。 か、この子やっぱり学校に行ってない分
うん。
そういう話をする人が欲しいんだなとか。
うんえん
うん。
とにかく子供から教えてもらうっていうことって大事なんだなと思って。
あ、あ、
そうするとすごく喋るので子供って。
あ、ほのさん、そういうことはお母さんと喋るのは
はい。
嫌じゃなかったっていうか楽しかった。
楽しかったと
思ってます。うん。
学校に関してのなぜ行けないかとか嫌な思 したこととかではなく、そういうこう好きなことだったら話せるなっていう風に感じたと。
うん。そうですね。その時は楽しかった趣味の話とかができるから
なんかその時はやっぱりその学校のことについて触れられないので
うん。うん。
ま、普通に話せるかなって。
うん。
あの、そういう時間を経てですね。
はい。
ち恵さんは心理カウンセラーの資格を取るで野さんは専門学校に進むという、ま、選択をされてきますけれども その辺りは何かきっかけがあったんですか?
え、私はもう娘の気持ちがまず知りたいっていうのが 1 番で心理カウンセラーの資格を取りました。
うん。
私はもうアニメが好きだったので
イラストの専門学校に行きたいなと思って色々調べていくことを決めました。
うん。うん。
自分が 1 番その絵を書いてる時間が楽しかったので
うん。
はい。
それがちょっとでも将来役に立てばなっと思って
うん。
見えました。
うん。 うん。
そうした経験を元にこう今多くの方たちの不投校の悩みに向き合ってるということですけれども
はい。
普段感じることってどんなことですか?
いや、私も今はその親御さんを見ていて
はい。
本当に過去の自分を見ている
うん。
状態です。今正直
ああ、
私はすごくうるさいだったので
子供に本当に口を出し
うん。
子供に選択をさせないんですね。
うん。うん。 できればそっちの道にするが安心だよとか、もう勝手なこれ親の安心だけなんですね。
うん。
うん。
うん。でもやっぱりそうなると子供って移縮してしまって
うん。
で、また不登校から抜け出せなかったりするので
うん。うん。
不登校でも明るい未来があるってことは本当に知って欲しいですし、
今本当にたくさん悩んでる親御さんには少しでも思い、その悩みの荷物を下ろせれるお手伝いができればいいなってことはいつも思ってますね。そうだ。
うん ほさんはいかがですか?
私はやっぱり自分は結果的にはやっぱりもう今仕事ができるようになったんですけど
やっぱり今現状不投校の子たちはどういう風にしていけばいいのかなっていう風に不安がいっぱいあると思うし、親にもきっと
高校どうするの?じゃあ仕事どうするの?大学どうするのってきっと言われると思うんです。
うん。うん。
でもそういうのがすごい嫌だなとか辛い気持ちになるし もう、もうはっきり言うとうざいなって思って
と思うんですけど。
うん。
意外とみんな自分で考えてて
うん。
自分が思った通りにできるかはわかんないけど
でも
自分なりに色々考えてるんだよっていうのはお父さんお母さんたちにはしといて欲しいなって思ってます。
うん。ちさんから見てなかなか難しいぞと思うような状況ってのはどういう状況だったりします?
あの、親御さんだけじゃなくておじいちゃんおばあちゃん前出てくる過程があるんですね。 ああ。
で、やっぱりおじいちゃんおばあちゃんって、ま、本当にこれ昭和の考えなんですけど、どうしてもいい学校入ればいいとこに就職できるっていうのがまだ頭にやっぱりある方がたくさんいらっしゃっていて、
そうなるともう本当に子供を潰してしまうんですよね。
うん。
それでもやっぱりお父さんもお母さんも
おじいちゃおばあちゃんに対してちょっと遠慮があるというか。
うん。うん。
うん。まずそのお父さんお母さんからカウンセリングしなきゃいけないなってありますね。
うん。そうですよね。
うん。うん。
今ちょうど ね、新しい学校になったりとか
はい。
学年になって、また新しい悩みにぶつかってしまう
そうなんです。
お子さんもいるでしょうね。
そうなんです。ま、 1 番多いのはやっぱりゴールデンウィーク系に
うん。
学校行きたくないっていう子がたくさん出てくるんですけど。
大型連休の後にはい。
そうなんです。はい。なのであんまりこう学校になんかきしぶるような様子が見られたら
うん。な
んで学校行けないのとか質問攻めにするっていうのはやめてくださいっていうのは伝えてますね。
で、黙 たら必ず子供は喋るから、例えばおやつ出した時とか夕飯の時に実はこういうことがあってさってポロっと言うから子供がポロっと話したことはちゃんと聞いてあげて
うん。
で、嫌なことがあった嫌なことがあったでちゃんと受け止めてあげる。嬉しいことがあったり一緒に喜んであげてもその形を必ず守ってくださいってことは伝えてます。
うん。子供が言うの待つってことですね。
そう。やっぱりずっと質問されると大人もそうですけど嘘つきますよね。例えば仕事から帰ってきた時に家族から今日仕事どうだった?お昼何? 食べたのとか、どんななんかめんどくさい案件があったのとか前に聞かれたのと嫌ですね。それ
めんどくさいですもんね。答えるのがね。
そう、そうなんですよ。そうなんですよ。で、子供もやっぱりめんどくさいので
うん。うん。
で、結局答えたら答えたで、またそっからお母さんたち行って
ね掘りは掘り聞くじゃないですか。
うん。心配だからね。
うん。
そう、そうなんです。私もそうだったので。だから聞きたい気持ちを来らえてっていうのはいつも伝えて。うん。
はい。
ほさんはいかがですか? はい。私はやっぱり学校行けなくなった理由は様々だけど
うん。
将来はやっぱり不安だろうけど
親に言われて焦る気持ちもあるかもしれないけど
うん。
ゆっくりゆっくり自分でしたいこととか考えたりとかどうしようかなって考えたら
うん。
ちゃんといい風に将来向いていくと思うから大丈夫だよって私はそれを 1 番いいです。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
子供の を待つ
ていうのがとても印象的でしたね。
うん。大事な言葉でしたね。
はい。
で、え、娘のほのさんは今は好きだったことを仕事にイラストレーターとして仕事にして活躍しているということなんですね。
はい。
ここからはNotebookLMで整理したもの
小沢ちえさんと娘のほのさんが行う不登校に悩む親子へのカウンセリングにおいて、「子供がポロッと話したことを聞く」という点は、特に親へのアドバイスとして非常に重要な位置づけがされているようです。これは、カウンセリング全体の流れや、小沢親子自身の経験を踏まえた上での重要なポイントとして強調されています。
カウンセリングのポイントとして、まず小沢親子は、親と子は別れて話を聞くというスタイルをとっています。相談者の親は千恵さんが、お子さんの話はほ野さんが聞くという形です。これは、親は親同士、子供は子供同士で、それぞれがより話しやすい環境を作るためです。娘のほ野さんは、相談者の子供とゲームをしたり、アニメの話をしたり、YouTubeを見たりするなどして、共通点を見つけ、相手の心を開くことを得意としています。これは、ほ野さん自身の不登校経験 や、母親である千恵さんとアニメの話を通じて再び仲良くなれた経験 に基づいています。その後、親子がお互いの意見を伝え合う対話の時間を設けています。
このようなカウンセリングのプロセスの中で、親が子供にどのように接するべきかという点について、特に「聞く」姿勢が強調されています。特に、ゴールデンウィーク明けなど、学校に行きしぶる様子が見られた場合について触れられています。
•
親が心配するあまり、「なんで学校行けないの」と質問攻めにすることはやめてほしいと伝えられています。
•
質問攻めをすると、大人でもそうであるように、子供もめんどくさく感じたり、嘘をついたりすることがあります。さらに、子供が答えたとしても、親は心配からさらに掘り下げて聞いてしまう傾向があることも述べられています。千恵さん自身もかつてそうだったと述べています。
•
そうではなく、親が「黙ったら必ず子供は喋る」という考え方が提示されています。
•
例えば、おやつを食べている時や夕飯の時など、リラックスした状況で、子供が「実はこういうことがあってさ」とポロッと話すのを待つことが推奨されています。
•
そして、子供が「ポロッと話したことはちゃんと聞いてあげて」、その内容を「ちゃんと受け止めてあげる」ことが非常に重要であると強調されています。
•
嫌なことがあったなら「嫌なことがあったでちゃんと受け止めてあげる」、嬉しいことがあったなら「一緒に喜んであげる」といった、子供が話した内容の「形を必ず守って」聞くことが伝えられています。
•
これはつまり、「子供が言うの待つ」ということであるとインタビュアーが確認しており、千恵さんもそれを肯定しています。千恵さんは、この「聞くたい気持ちを来らえて」子供が話すのを待つことが重要だと伝えていると述べています。インタビュアーも、この「子供の言うのを待つ」という点が「とても印象的でした」と述べており、「大事な言葉でしたね」と評価しています。
この「子供がポロッと話したことを聞く」という姿勢は、単に情報を得るためだけでなく、子供への信頼を示し、安心感を与えるためのアプローチです。これは、千恵さんが自身の経験から、子供に口を出しすぎたり、子供に選択をさせず親の安心を優先してしまったり することが、かえって子供を委縮させ、不登校から抜け出せなくなる可能性がある と感じていることと関連しています。また、おじいちゃんおばあちゃん世代の「いい学校に入ればいいとこに就職できる」といった考え方 が、子供を「潰してしまう」可能性がある という指摘からも、子供自身の気持ちや考えを尊重し、それを聞く姿勢が重要であることが示唆されます。
ほ野さんも、不登校の子どもたちに、将来への不安があるかもしれないが、「ゆっくりゆっくり自分でしたいこととか考えたりとかどうしようかなって考えたら」「ちゃんといい風に将来向いていくと思うから大丈夫だよ」と伝えており、これもまた、親が焦らせるのではなく、子供が自分で考え、自分のペースで進むことを待つ姿勢、そしてその過程で子供の考えを聞き、見守ることの重要性を示唆しています。
したがって、「カウンセリングのポイント」というより大きな文脈において、「子供がポロッと話したことを聞く」ことは、小沢親子が提供するサポートの中心的な要素の一つであり、特に親が子供との信頼関係を再構築し、子供が自分の気持ちや考えを安全に表現できる環境を作るための、忍耐強く、かつ受容的なコミュニケーションの姿勢として位置づけられていると言えます。これは、子供を質問攻めにして追い詰めるのではなく、子供が自ら心を開いて話してくれるのを待ち、その言葉を頭ごなしに否定せず、そのまま受け止めることが、子供の心をほぐし、解決の糸口を見つける 上で不可欠であるという考えに基づいています。
カウンセリングのポイントというより大きな文脈において、これらのソースは親子間の対話を効果的に進めるための「仲立ち(中立ち)」の重要性を強調していると言えます。これは、不登校に悩む親子が抱える特有のコミュニケーションの問題に対処し、解決の糸口を見つけるための中心的なアプローチとして位置づけられています。
具体的には、以下のような点が挙げられます。
1.
カウンセリングのプロセスにおける「仲立ち」の位置づけ:
◦
小沢千恵さんと娘のほ野さんのカウンセリングでは、まず親と子が別れて話を聞くスタイルをとります。千恵さんが相談者の親の話を、ほ野さんが子供の話を聞きます。これは、それぞれが「一番話しやすい」環境を作るためです。
◦
娘のほ野さんは、相談者の子供とゲームやアニメ、YouTubeなどを通して共通点を見つけ、子供の心を開くことを得意としています。これは、ほ野さん自身の不登校経験や、母親とのコミュニケーション回復経験に基づいています。
◦
別々に話を聞く時間を設けた後、親子がお互いの意見を伝え合う対話の時間が設定されます。
◦
この対話の際に、小沢千恵さんとほ野さんが「立ち会って親子の対話を仲立ちするような」役割を担います。
2.
「仲立ち」の具体的な役割と目的:
◦
「仲立ち」は、子供からの気持ちを(ほ野さんを通して)親に伝え、親としての気持ちを(千恵さんや相談者の親が)子供に伝えることで行われます。
◦
この役割の目的は、親子が「うまくお互いの意見を伝え合って」、現在の環境を「少しでも軽くすることができるのか」という「解決の糸口を見つける」ことです。
◦
これは、単に両者の意見を伝えるだけでなく、感情的になりがちな親子のコミュニケーションを整理し、建設的な話し合いへと導く役割を果たしていると考えられます。
3.
「仲立ち」が重要である背景:
◦
ソースからは、不登校の状況にある親子間では、コミュニケーションがうまくいかなくなっている様子がうかがえます。例えば、ほ野さんは、母親に自分の気持ちをほとんど言えなかったと述べており、母親からの「学校どうするの?」という問いかけが辛かったと感じています。
◦
また、母親である千恵さんも、以前は子供に口を出しすぎたり、子供に選択をさせず親の安心を優先してしまったりした経験を語っており、それが子供を萎縮させてしまう可能性があると認識しています。
◦
このような状況では、親子だけで話し合おうとしても、感情的な衝突が起きたり、本音を伝えられなかったりする可能性が高いと考えられます。
◦
第三者であるカウンセラーが「仲立ち」として入ることで、親子の間に安全な空間を作り、それぞれの気持ちや考えが冷静に伝えられ、相手に受け止められやすくなります。
4.
「聞く」姿勢との関連性:
◦
前回の議論でも触れた「子供がポロッと話したことを聞く」という親へのアドバイス は、親が子供の言葉をそのまま受け止める練習であり、子どもの安全基地となるための重要なステップです。
◦
「仲立ち」による対話の場は、親が学んだ「聞く」姿勢を実践する場ともなり得ます。カウンセラーのサポートを受けながら、子供の気持ちや考えを直接聞き、それを受け止める経験を積むことができます。
◦
親が「黙ったら必ず子供は喋る」という考え方 の実践が難しい場合でも、「仲立ち」がいることで、子供の言葉を丁寧に引き出し、親がそれを聞くサポートを受けることができます。
結論として、「カウンセリングのポイント」という文脈において、小沢親子が提供する「親子の対話の仲立ち」は、別々にじっくりと話を聞いてそれぞれの本音を引き出した上で、安全かつ建設的な方法でその気持ちや考えを伝え合うための、不可欠なステップです。これは、これまでうまくいかなかった親子のコミュニケーションを修復し、お互いを理解し合い、共に不登校という状況からの解決策を探るための重要なサポート機能として位置づけられています。特に、親自身がかつての千恵さんのように子供に干渉しすぎてしまったり、子供がほ野さんのように親に本音を言えなくなってしまったり している状況において、この「仲立ち」は、親子の関係性を立て直し、前に進むための鍵となると言えます。
「難しい状況」というより大きな文脈において、これらのソースは、祖父母が不登校の問題に関わってくる家庭が、カウンセリングを行う上で特に困難な状況となりうることを述べています。小沢千恵さんは、カウンセリングにおいて「難しいぞと思うような状況」の一つとして、「親御さんだけじゃなくておじいちゃんおばあちゃん前出てくる過程がある」 と具体的に挙げています。
なぜ祖父母の関与が難しい状況を生むのか、ソースからは以下の点が読み取れます。
1.
古い価値観の持ち込み: 祖父母の中には、「どうしてもいい学校入ればいいとこに就職できるっていうのがまだ頭にやっぱりある方がたくさんいらっしゃって」 います。これは、小沢さんが「昭和の考え」 と表現するように、学歴や学校に通うことそのものを強く重視する価値観です。
2.
子どもへの圧力と影響: このような価値観を持つ祖父母が不登校の子どもに関わることで、「本当に子供を潰してしまう」 可能性があると千恵さんは指摘しています。学校に行くことを強く要求したり、子どもの気持ちや状況を理解しようとしなかったりすることが、子どもにとってさらなる重圧となり得ることを示唆しています。
3.
親の立場と葛藤: 親(父・母)は、祖父母の意向に対して「おじいちゃおばあちゃんに対してちょっと遠慮があるというか」 状況にあることが多いようです。これは、親が子どもの不登校問題にどう向き合うかという際に、祖父母の意見や期待との間で板挟みになり、適切な対応を取りにくくなる要因となります。親自身が子どもの気持ちに寄り添おうとしても、祖父母からの圧力によってそれが難しくなるケースが考えられます。
このような背景から、千恵さんは、祖父母が出てくる家庭の場合、「まずそのお父さんお母さんからカウンセリングしなきゃいけないなってありますね」 と述べています。これは、祖父母の関与が、親自身が子どもの問題にどう向き合うか、どう行動するかという点に大きな影響を与えるため、まずは親の意識や対応を変えるためのサポートが必要である、という認識を示しています。
したがって、「難しい状況」という文脈において、これらのソースが「祖父母が出てくる家庭」について言いたいことは、祖父母が持つ旧来の価値観が子どもに過度のプレッシャーを与え、さらに親の対応を難しくさせるため、カウンセリングを進める上での特有の障壁となる、ということです。このような場合、カウンセリングはまず親の立場や対応の整理から始める必要が出てくる、という点に焦点が当てられています。
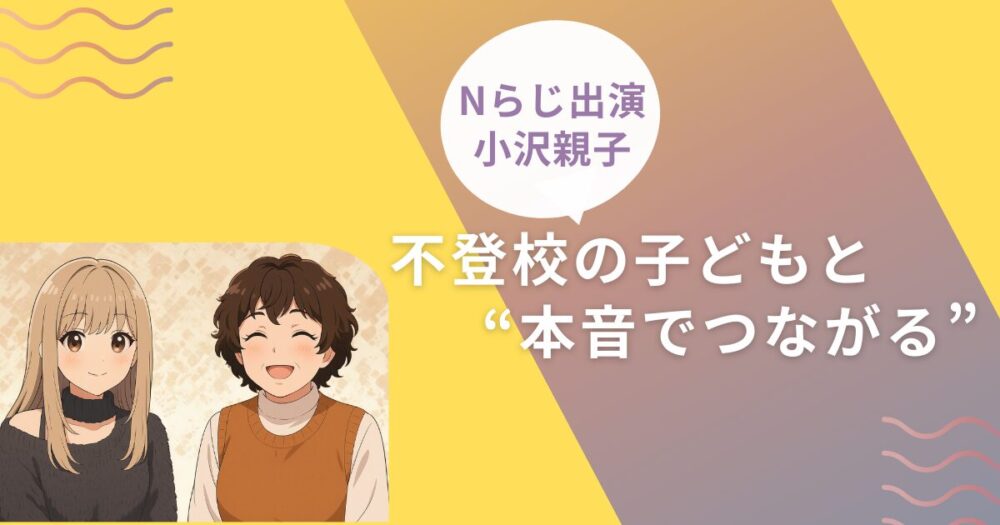
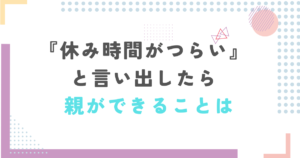
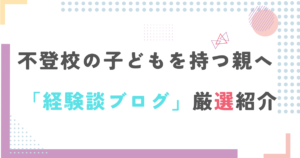
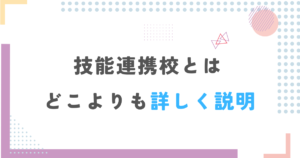
コメント