この記事を書いているのは、4月中旬。ちょうど進学・進級シーズン真っただ中です。
この時期は、新しい環境にわくわくする一方で、不安や緊張に押しつぶされそうになる子どもも少なくありません。
 Kon
Konわが家も、例外ではありませんでした。
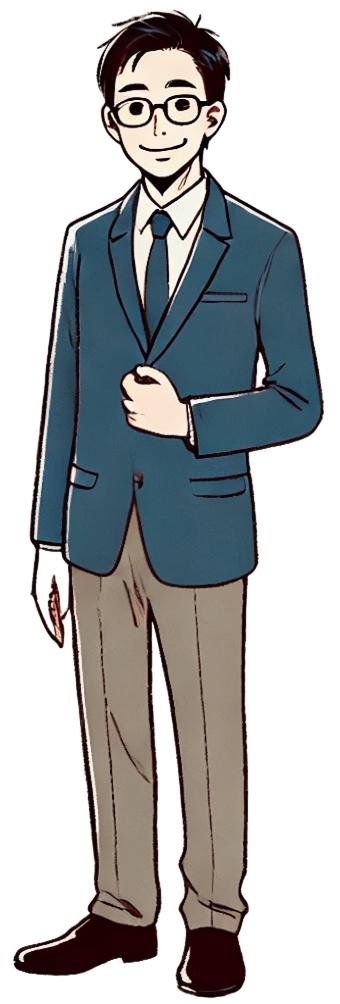
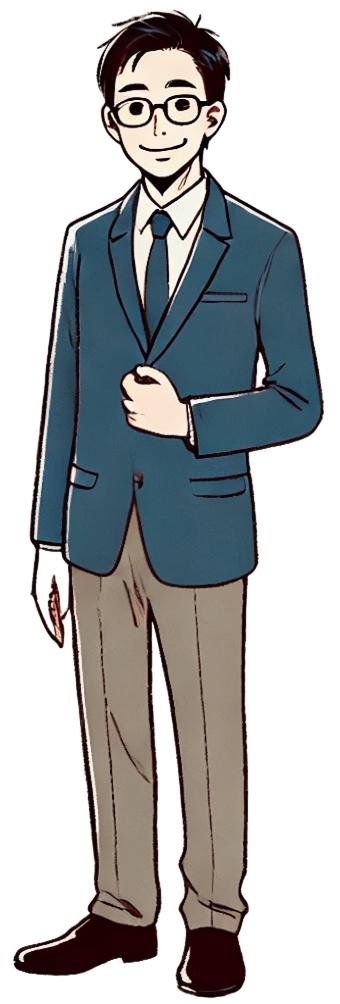
- もと中学校の教員 35年間勤務
- アドラー心理学、認知行動療法、コーチングなどを学ぶ
- 「子どもに一生懸命でない保護者はいない」が信条
- 現在も教育関係の仕事に従事
- 自分の子どもが2人とも不登校を経験。
- その経験から不登校についての発信を始める。
サイト管理者の子どもが不登校傾向である、ということはこのサイトで何度か触れてきました。
いろいろなことを乗り越え、なんとか兄は大学に進学していますが、娘が今年度から高校に進学しました。
その娘が進学早々「登校渋り」をしたのです。
- 「初期不登校」は「行ってしまえばなんとかなる」という実践記録。
- 「登校渋り」に対する、サイト管理者家庭でのリアルなやり取り。
- 「登校渋り」に対応したときのサイト管理者の心の動き。
- サイト管理者が考える妻との連携。
- 「登校渋り」のときの学校への連絡のコツ。
「行ってしまえばなんとかなる」
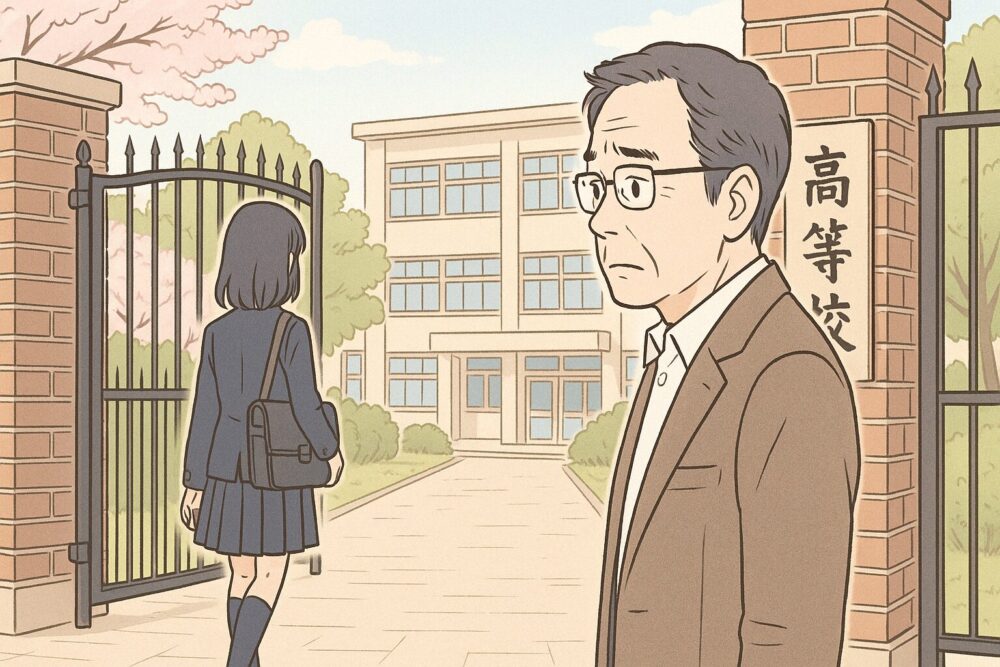
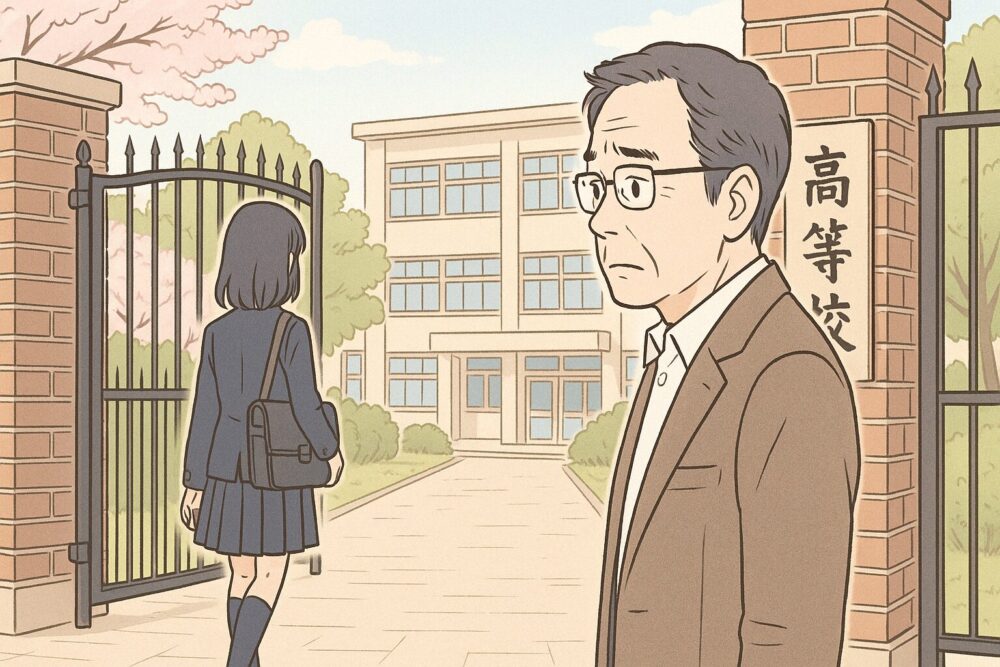
娘が登校渋りを始めたのは、この記事を書いたちょうど2週間前です。現在なんとか娘は学校に登校しています。
大きな要因は
「慣れた」
だけだと思います。
そもそも娘の高校への当初の心配は「考えすぎ」だったと思うのです。
今の子供達は
- 失敗を極度に恐れる。
- 知らないところにいくことに大きな抵抗がある。
という傾向があります。
サイト管理者の娘も例外ではなかったようです。
そこに自閉傾向が加わり、高校というはじめての環境を極度に恐れていたのだと思うのです。
ですから
「行ってしまえばなんとかなる。」
のです。



中学校現場に30年以上勤めたサイト管理者の肌感では初期不登校の半分はこのパターンだと思います。
奇しくも今回「自分の娘」がそれを証明してくれたようなことになりました。
以下その顛末をご紹介します。
「大丈夫かな」と思っていた矢先の、登校渋り
うちの娘は今年度から高校生になりました。
同じ中学から進学した子はおらず、完全にひとりでのスタート。
それでも進学先は本人が何度も考え、納得したうえで選んだ高校でした。
入学式も、明るい表情で参加。
「まずまず順調かな」と思っていたのですが……その夜、娘の様子が一変しました。
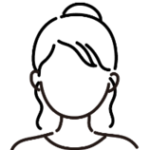
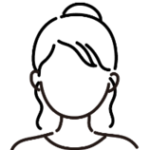
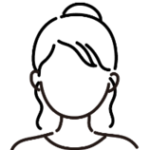
「寝られない」
「お腹が痛い・・・」
――このパターン、うちでは“いつものやつ”です。
もともと腹痛を起こしやすく、緊張やストレスがあると体に出てしまいます。
ひどいときは嘔吐してしまうことも。
この夜は幸い吐くことはなかったのですが、眠れないまま朝を迎えました。
「今日休ませたら、行けなくなる」――妻の判断


朝、娘の顔色は悪く、「気持ち悪い」と繰り返します。



私としては休ませても良いのでは……と思いましたが、妻は違いました。
「今日休んだら、明日以降もっと行けなくなる。とにかく行かせよう。」
強い口調で、私に出勤の遅刻を依頼し、娘の送迎を私に託します。
正直、私には少し強引すぎるようにも感じましたが、妻には確信があったようです。
1時間の送迎と車中での爆睡
車で高校までは1時間ほど。
出発は始業ギリギリの時間でした。
道中、娘はほとんど眠っていました。
前夜眠れなかったこともあるでしょうが、心身が限界に近かったのだと思います。
学校が近づいたところで「もうすぐ着くよ」と声をかけると、ぼんやりと目を開けました。
「行ける?」と聞くと、小さな声で「なんとか……」



「しばらく車で待機してるから何かあったら電話しなさい」伝えました。
車を降りて昇降口へ向かう娘の背中は、明らかにフラフラでした。
無事授業に参加 けれど「楽しい」は聞こえてこない
1時間ほど、公園の駐車場で待機していましたが、連絡は来ませんでした。
私はそのまま職場に向かいました。
夕方、帰宅すると、娘はぐったりした様子で帰ってきていました。
食欲はなく、昼食も取れなかったそうです。
それでも、「全部授業には出た」とのこと。
私も、そして妻も、まずはそれだけで十分。
ただ、夜、妻と話すうちに娘はポロリと涙をこぼしはじめました。
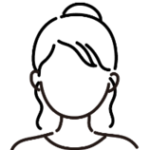
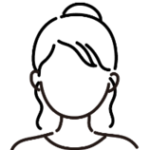
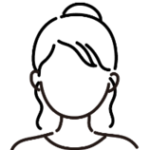
「中学の友達は、みんな“高校楽しい”って言ってる。
私だけつらい。」
ラインで交わされる友人たち反応が「楽しい」というものが多く、自分とのギャップを際立たせてしまったようでした。
おそらく、娘は悩みを共有したくてラインを見たのでしょうけれど、逆効果になってしまいました。



SNSはそういう意味でも両刃ですね。
「だから近くの学校にしなさいって言ったのに」と妻が口にすると、さらに泣き出してしまい――。
それでも、妻が頭を撫でて、「明日も行けないようなら、今度は私が送ってくから」と声をかけると、少し落ち着いたようでした。
「なんとか登校」は続く
翌朝、やはり娘は動けません。
前日より睡眠がとれた分、体はマシなようでしたが、気持ちは重そうです。
それでも、声をかけ、背中を押して、なんとか登校。



「列車ではいけない」とのことでその日は妻が車で送っていきました。
帰宅して娘に今日の様子を聴きました。
「駅まで友達と歩いて帰ってきた」
「よくまぁ歩けたね」というと小学校より近い、とのこと。
なんとなく、表情に生気が戻ってきました。
娘の負担にならない程度に学校での出来事を聞くと、いろいろ話してくれました。
次の日は部活動見学があるそうです。
「自分の興味のある部活動に行ってみたい」と話してくれました。



娘はこれまでも部活動や、学校外の習い事で救われてきました。
なんとか、自分の好きなものをやり続けることができればいいな、と思い、
「とにかく好きなものをやりなさい」
とだけ伝えました。
「慣れてきた」と言うにはまだ早いけれど


3日目の朝。中学時代より1時間以上早く起きなければならない生活に、ようやく少し慣れてきたようです。
とはいえ、食欲はなく、ぼーっとしたまま食卓につく娘。
それでも「今日は列車で行く」とのこと。
駅まで私が送っていく途中で、
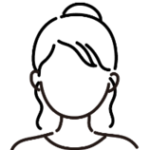
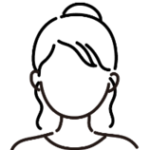
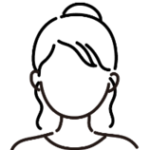
「定期って本当に乗れるのかな」 「席空いてるかな」
と、ぽつりぽつりと不安をこぼします。
一回練習はしましたが、何と言っても「初」列車通学です。
「そうだね、ちょっと心配だね」と返答しておきました。
車を停めると、割と元気に「行ってきます」と言い残して、時間ギリギリの列車に乗り込むことができました。
私達夫婦はここで一安心。
職場でもちょっと気がかりでしが、特に心配なラインも入らず一日を終えることができました。



その日の夜、「部活見学が楽しかった」と話してくれたのが、少しだけ希望でした。
現時点でのまとめ
まだ「高校生活に慣れた」とは言えません。
「楽しそう」と言える状況でもありません。
ただ、今の娘は、「なんとか登校している」という状態です。
ここまで家の娘の「登校渋り」について皆さんに聞いていただきました。
娘や妻とのやり取りもある程度書きました。
同じような「登校渋り」で悩んでいる方にとって少しでも参考になったら、と思っています。



ここで経過と対応を一旦下記にまとめておきます。
登校渋りの前兆
- 入学式の翌夜に腹痛と不眠
- 持病のように抱えているストレス反応
要因と背景
- 知り合いがいない高校生活
- よそよそしい教室の空気感
- 自閉傾向のある娘にとって、馴染みにくい環境
- SNSで見る“楽しそうな友達”とのギャップ
我が家の対応
- 妻が“緊急事態”として即座に判断し、背中を押す。
- 私は送迎やフォローに回る。無理をさせすぎないよう、娘の様子を見ながら声かけ。
- 同居の祖母にも逐一情報を共有して、家庭全体で支える。
「司令塔は一つ」が我が家のルール


対応の中で大切にしていることがひとつあります。
それは、「司令塔は一つ」という考え方。
我が家では、緊急時の判断は妻が担います。
これは私が妻に逆らえないからではなく(笑)、母親としての“勘”を信頼しているからです。
私の役割は、その決定を尊重しながら、具体的に「今何ができるか」を考えて動くこと。
家庭内での対立は、子どもにとって大きなストレスになる
夫婦のうちどちらかが一方的に考えを押し付けると関係はギクシャクしてしまいます。
「ギクシャク」だけならまだいいのですが、こじれると夫婦のトラブルに発展してしまいます。
子どもの問題が家庭でこじれる大きな原因のひとつは「司令塔が別れてしまう」ことです。



それを避けるためには、家族全体が同じ方向を向くことが必要です。
詳しくは「子どもが不登校になった時学校の先生に助けてもらう9つの方法」に書いてありますが、ひどい場合は責任の押し付けが始まるのです。


そのような状態を子どもが見ていて気持ちが休まるわけはありません。
ましてやそのようなことが普段からあると、子どもは親に相談すことができなくなってしまいます。



「自分が夫婦のトラブルの原因になっといる」と思ってしまうからです。
問題を抱える子どもが親に助けを求めることができない大きな原因でもあります。
ですから、どちらかが「司令塔」でどちらかか参謀となるのが理想的だと思います。
少なくとも子どもから見たときに
「自分のために家族は協力して努力してくれている」
と感じられることが重要です。
サイト管理者の周囲を見ていると、うまくいっているところは奥さんが司令塔の役割を担っている家庭が多いように思います。
ただ、誤解しないでいただきたいのは主従の関係ではない、という点です。
ちょうど三国志の劉備玄徳と諸葛孔明のような関係と考えていただくといいかもしれません。
サイト管理者は自分の役割は諸葛孔明だと思っています。



妻がどう思っているかは不明ですか・・・・
元教員からのアドバイス:「正直な相談」がカギ
最後に、元中学校教員としてお伝えしたいことがあります。
それは、「学校への連絡は、正直に」伝えること。
「体調不良」とだけ伝えると、後に本当の事情が知られてしまったときに、先生は「ごまかされた」と感じることがあるからです。
一方、「登校渋りがありました」と最初に相談しておけば、先生も配慮をしやすくなります。



例えばグループ活動のときの席の配慮や、グルーピングのやり方などです。
先生方も人間です。相談されると「頼られている」と感じて、動きやすくなるものです。
まだ始まったばかりの高校生活
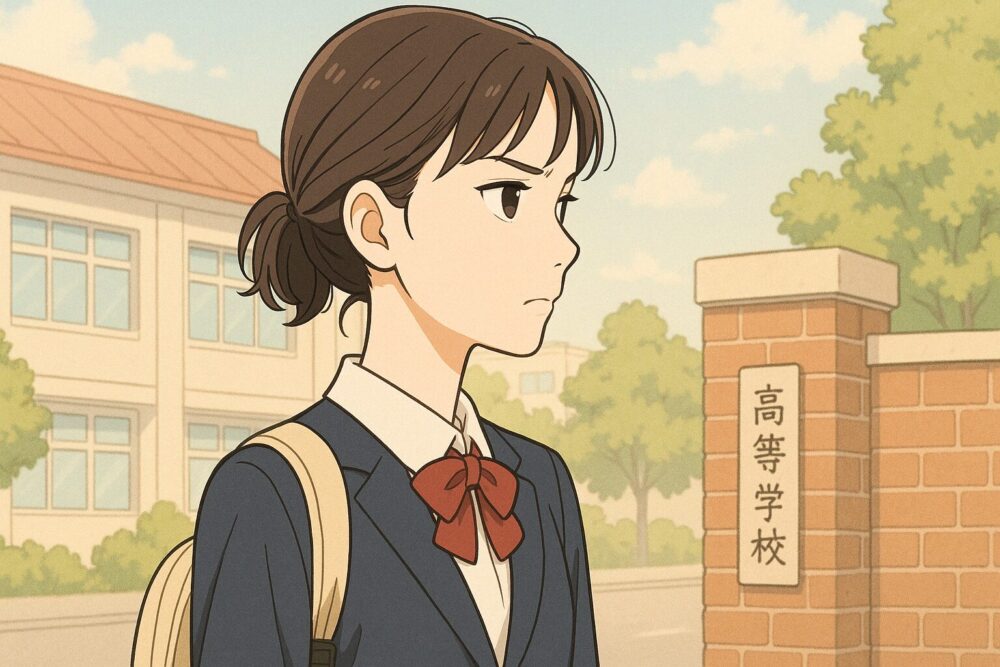
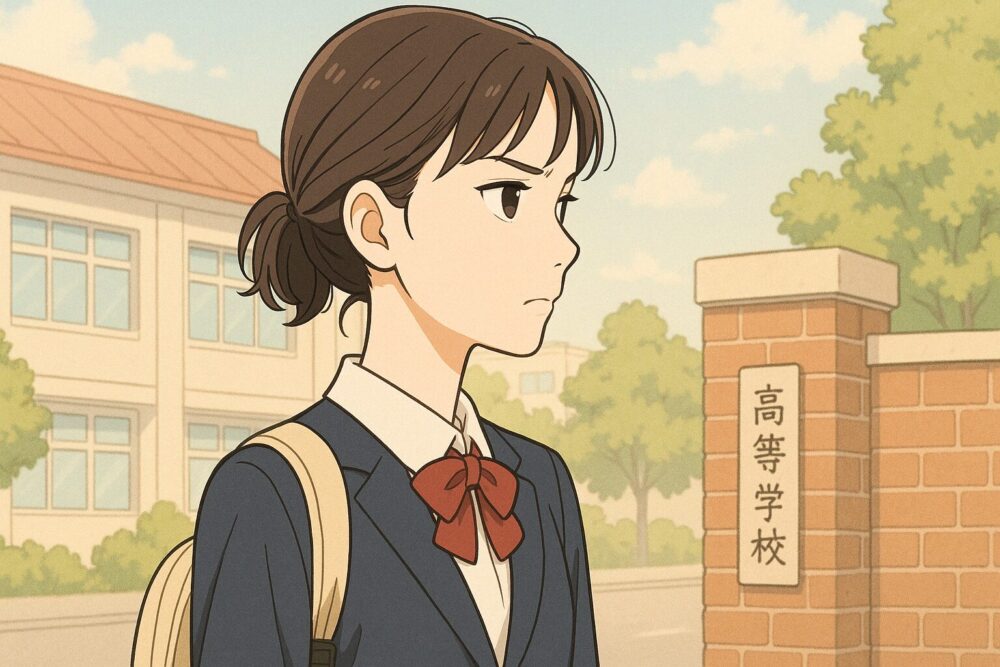
「このまま、なんとか続けてくれたら」
それが今の私たち夫婦の正直な願いです。
明日からは土日。少しは休める……はずですが、不登校傾向のある子にとっては、
この「一息」がまた曲者。
サザエさんが流れる時間に、私はちょっとだけ身構えるわけです。
ご家庭で同じような悩みを抱える方がいたら、少しでも参考になれば幸いです。
焦らず、でも丁寧に、子どもを支えていけたらと思っています。
余談ですが、娘の入学式のとき駅前を家族で歩いていたら、トライ式高等学院が目に入りました。
いざとなったら「ここに行くか」と冗談交じりに娘と話をしました。
実は私の中では半分本気でした。
けれど
「不登校になっても次の手がある」
とサイト管理者自身が思っていたことは心にゆとりを持てた要因です。
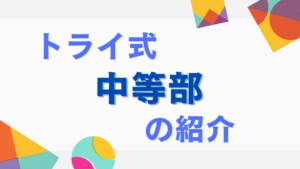
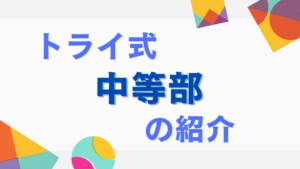
まとめ
- 登校渋りは「突然」始まることがある
入学式翌日の夜に体調不良が始まり、初登校が困難になった。 - 体調不良はストレスのサイン
腹痛や不眠は、環境変化への不安や緊張が引き金となって現れた。 - 「今日休んだら行けなくなる」判断も必要
妻の強い判断で初登校をなんとか実現したことが、流れをつくった。 - 登校は「行ってしまえばなんとかなる」ことも多い
心配していたことが実際には起こらず、徐々に「慣れ」が見られた。 - 子どもは「比較」で落ち込みやすい
SNSで見る“楽しそうな友達”の姿が、逆に心を沈ませてしまった。 - 家庭の中で「司令塔」は一つにするのが理想
夫婦で役割を分担し、意見が割れないように協力する姿勢が大切。 - フォロー役も重要な存在
判断は妻が、送迎・見守り・外との連携は夫が――家庭内で自然な分担を意識。 - 学校には「正直に」相談するのがベスト
「登校渋りがある」と最初に伝えることで、先生側の理解と配慮が得られる。 - 「好きなこと」が登校継続のきっかけになる
部活見学が少しの前向きさにつながった。興味関心は大切な支え。 - 「登校しているだけで十分」と思える視点を持つ
無理に「楽しんでいるか」を求めず、まずは“通えていること”を認める。
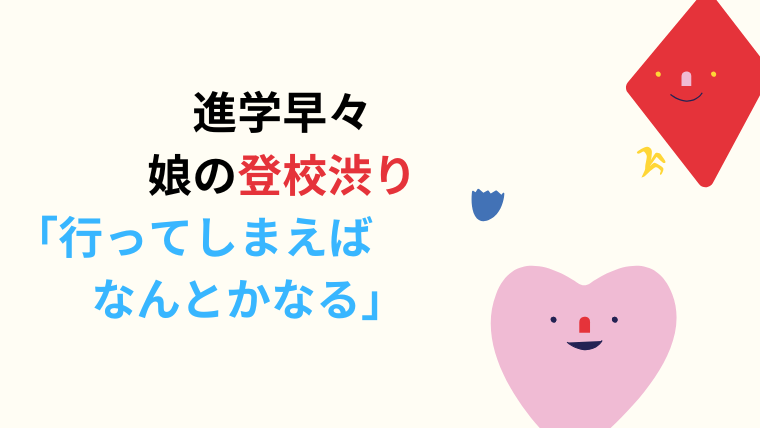
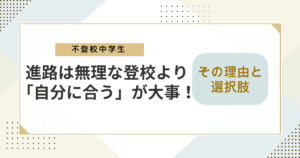
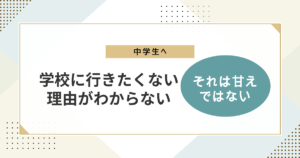
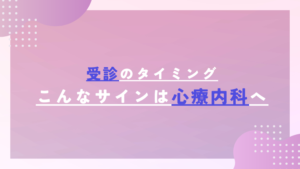
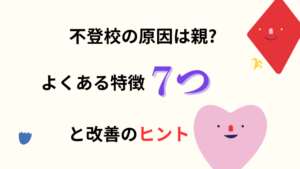
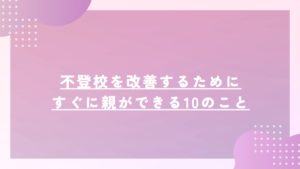

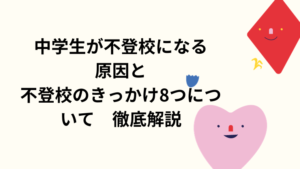
コメント